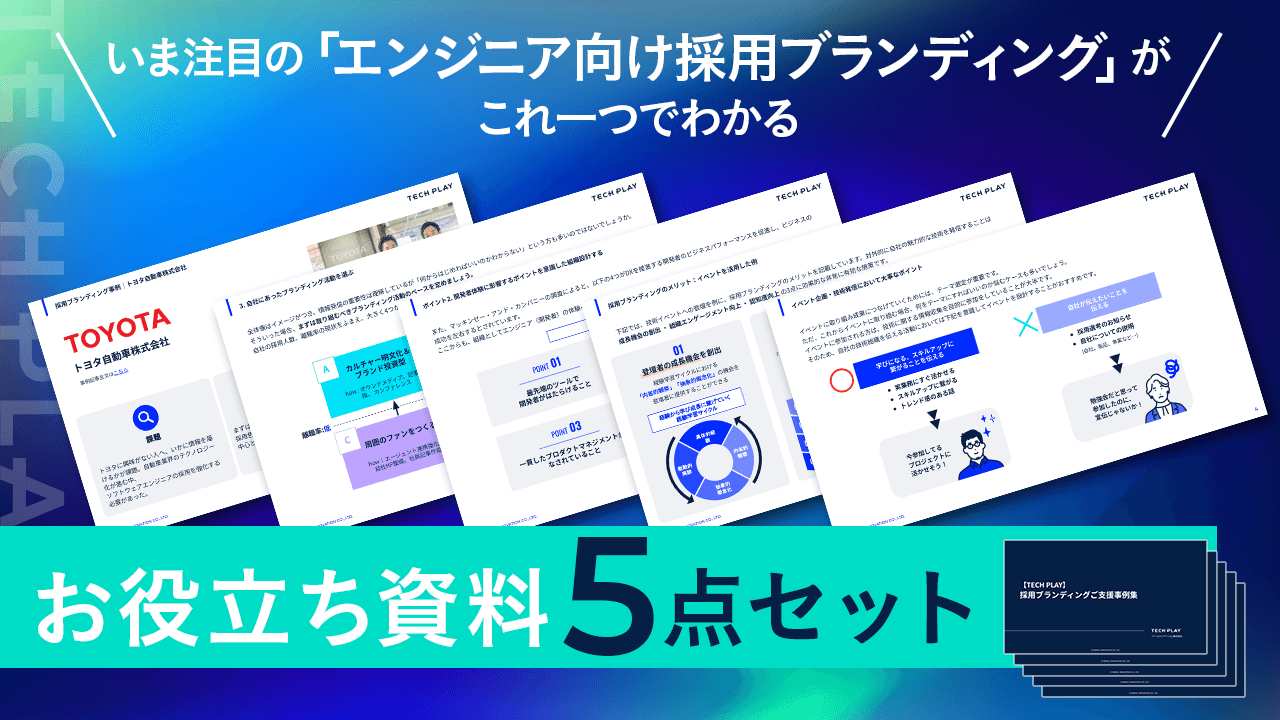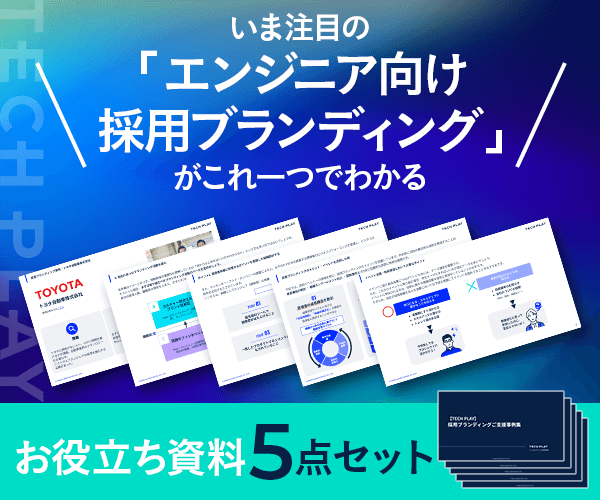エンジニア採用は難しい?苦戦する理由とやるべき17の対策【成功事例あり】
エンジニア採用において、「なかなか応募が集まらない」「ようやく内定を出しても辞退されてしまう」「採用できてもすぐに離職してしまう」といった悩みを抱えていませんか?
近年、IT人材の不足が深刻化しており、優秀なエンジニアの採用競争はますます激しくなっています。
エンジニア採用が難しいのは、単なる人材不足だけでなく、採用市場の変化や企業側の課題など、さまざまな要因が影響しているからです。
そこで本記事では、エンジニア採用が難しくなっている原因や、採用を成功させるためにやるべき17の対策をご紹介します。
目次
エンジニアの採用は難しいと感じる企業が抱える悩み5選
「エンジニアを採用したいのに、なかなか応募が集まらない」「ようやく内定を出しても辞退されてしまう」といった悩みを抱えていませんか?
エンジニア採用は、他の職種と比べても特に難易度が高いと言われています。
本章では、現状を正しく把握するために、多くの企業が直面しているエンジニア採用に関する5つの代表的な悩みについて解説します。
企業が抱える、エンジニア採用に関する主な悩みは以下の5つです。
- エンジニアの応募者が集まらない
- 選考基準を満たすエンジニアの数が少ない
- 内定を辞退するエンジニアが多い
- 採用したエンジニアがすぐに離職してしまう
- 既存の採用手法だけでは採用が難しくなっている
それぞれ、詳しく解説します。
エンジニアの応募者が集まらない
せっかく採用枠を用意しても、応募が集まらなければ採用活動を進めることすらできません。
エンジニア採用が難しいと感じる企業の多くが、まずこの壁にぶつかります。
特に中小企業やスタートアップ企業の場合、大手企業に比べて知名度が低いため、求職者の目に留まりにくい傾向があります。
また、「応募はあるけれど、エンジニアとしての経験が浅い人ばかり…」と感じることもあるかもしれません。
「どうすれば、自社の魅力をエンジニアに知ってもらえるのか?」と、悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
選考基準を満たすエンジニアの数が少ない
ようやく応募が来たとしても、自社の求めるスキルや経験を持つエンジニアがなかなか見つからないといった悩みを抱えている企業も少なくありません。
優秀なエンジニアを採用したいと思うのは当然ですが、実際には即戦力となる人材は限られており、競争も激しくなってきています。
「選考を進めても、結局どの候補者にも決められない…」と採用活動が長引くほど、現場の人手不足も解消されず、ますます苦しい状況に陥ってしまうこともあるでしょう。
内定を辞退するエンジニアが多い
せっかく内定を出しても、内定を辞退されてしまうというケースも多いです。
エンジニアは複数の企業からオファーをもらうことが多く、内定を出したからといって、必ず入社してくれるとは限りません。
理由がはっきり分からないまま内定辞退が続くと、「どこを改善すればいいのか分からない…」と、採用活動に対する不安や焦りも募ってしまいます。
採用したエンジニアがすぐに離職してしまう
採用が成功しても、入社後わずか数ヶ月でエンジニアが退職してしまうケースも少なくありません。
どんなに優秀な人材でも、職場環境が合わなければ長く働き続けることは難しいものです。
早期離職が続くと、「また採用活動をやり直さないといけない…」と、企業にとっても大きな負担となってしまいます。
既存の採用手法だけでは採用が難しくなっている
これまでの採用手法が通用しなくなってきたと感じている企業も増えています。
特に、転職サイトや人材紹介サービスを利用していても、エンジニアからの応募が思うように集まらないケースが多いです。
エンジニアの転職市場は変化しており、従来の方法だけでは優秀な人材と出会える機会が減ってきています。
「今のやり方で本当に大丈夫なのか?」と不安を感じている採用担当者の方も多いのではないでしょうか?
エンジニア採用が難しい外部的・社会的な原因
エンジニアの採用が難しいと感じる背景には、企業の努力だけでは解決できない外部的・社会的な要因が絡んでいます。
具体的には、以下の6つの外部的・社会的な原因があります。
- IT人材が不足している
- IT人材の流動性が低下している
- 転職ニーズのあるIT人材が少ない
- 経験者の取り合いが発生している
- エンジニアの採用手法が多様化している
- フリーランスなど、エンジニアの働き方が多様化している
それぞれの原因について詳しく解説します。
IT人材が不足している
世の中のデジタル化が進む中、多くの会社が即戦力となるエンジニア人材を求めています。
しかし、社会的な需要の増加に対し、エンジニアは大幅に不足しているため、エンジニアと会社のマッチングがしづらくなってきています。
エンジニアの需要が高まっている理由は、以下のとおりです。
- 高度IT技術の発達
- DXに関する取り組み
- IT業界の成長
- 少子高齢化による労働人口の減少
IT関連を強化する流れは今後も続くと見られ、引き続きエンジニア不足が懸念されます。
経済産業省のデータによると、2030年には最大で約79万人ものIT人材が不足するといわれています。
ITエンジニア人材は売り手市場
転職サービスdoda(デューダ)が発表したデータによると、2024年8月のエンジニア(IT・通信)の転職求人倍率は12.41倍でした。
転職求人倍率から見ても、エンジニアは売り手市場であるといえるでしょう。
また、パーソルキャリアによる、2024年8月の業界ごとの有効求人倍率を見ると、IT・通信業界は7.45倍、DX推進が急速に進むコンサルティング業界も8.35倍と非常に高い水準になっています。
(「転職求人倍率レポート(2024年8月) | パーソルキャリア株式会社」をもとにパーソルイノベーション株式会社 TECH PLAY COMPANYが作成)
IT人材の流動性が低下している
エンジニアが不満に感じている労働環境や待遇を改善することで、既存のIT人材が外部に流出しないように、積極的な取り組みを行う企業が増えています。
そのため、高いスキルや豊富な実績を持つ優れた人材が、転職市場に出てくる機会は少ないと言えるでしょう。
また、「DX白書2023」によると、実際に流動する人材のイメージは下記図のとおりです。
(出典:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX白書2023」 )
IT企業・事業会社からの人材流動は「IT企業」「事業会社」「ベンチャー・スタートアップ企業」の間で発生していると言われていますが、転職する人材は事業会社で9%、IT企業で17%となっており、流動する人材は多くありません。
さらに、以下の経済産業省の調査によると、IT人材において転職ニーズが顕在化している層(より良い条件の仕事を求めて積極的に転職を行いたいIT人材)はわずか22%。
約72%という大半の人材が、いますぐは転職を考えていない「転職ニーズが潜在的な層」と考えられます。
(経済産業省 「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」をもとにパーソルイノベーション株式会社 TECH PLAY COMPANYが作成)
経験者の取り合いが発生している
新人ではなく即戦力となるキャリアを積んだエンジニアを求める企業・会社が多い点も、エンジニアの採用を難しくさせています。
即戦力が必要となる理由には、DX化に関する取り組みが挙げられます。
DXとはデジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)の略語で、デジタル技術により、業務効率化や新しいビジネスモデルを生み出し、競争上の優位性を確立する取り組みです。
これまではエンジニアといえばIT/Web業界での活躍が主でした。
コンサルファームやSIerなど、事業会社のクライアントに対して支援する側がエンジニア採用をする企業の中心であり、事業会社がエンジニアを求めるケースは、一部の先進的な大手企業に限られていたと言えます。
しかし、コロナ禍以降にDX化の波がきたことにより、自動車メーカーや電機メーカー、小売企業など事業会社のエンジニア内製化が進み、エンジニア人材の採用における競合環境が大きく変わってきています。
(参考:転職求人倍率レポート(データ)|パーソルキャリア株式会社)
エンジニアの採用手法が多様化している
転職市場におけるアクティブな求職者は、「人材紹介」、「求人媒体」、「ダイレクトリクルーティング」等の採用チャネルを利用しています。
しかし、これらのチャネルでは競争が非常に激しく、限られた転職顕在層を巡る争いが起こっています。
ニーズが生じると、多数の企業が競争に加わるため、転職ニーズが発生した際の情報伝達の難易度は高くなると言えます。
そのため、積極的に採用に取り組む企業の多くが「タレントプール」「リファラル」「イベント・勉強会」など、転職潜在層向けの施策を活用した採用ブランディングの取り組みを同時に進めていくことが多くなってきました。
ただ、社内には採用ブランディングの知見がなかったり、リソースが不足していることもあり、企業としても課題となっているケースも見受けられます。
フリーランスなど、エンジニアの働き方が多様化している
エンジニアの働き方が多様化していることも、エンジニアの採用を難しくしています。
副業やフリーランスなど、正社員以外でエンジニアになる手段が増えたことから、正社員に応募する求職者としてのエンジニアが減ってきています。
近年は自由な働き方を求めてフリーランスを望むエンジニアが増え、フリーランスをサポートするサービスも増えました。
本業のかたわら、副業としてエンジニアの仕事をする人も多くなってきています。
エンジニア採用が難しい企業の内部的な原因
エンジニア採用が難しいのは、外部環境の影響だけではありません。
実は、企業側の内部的な要因が採用のハードルを上げてしまっていることも多いのです。
どんなに採用活動に力を入れても、認知度が低かったり、ターゲットが不明確だったりすると、思うように成果が出ません。
また、エンジニアにとって魅力的な情報を発信できていないと、そもそも興味を持ってもらえないことも。
ここからは、企業が無意識のうちにエンジニア採用を難しくしている可能性のある「内部的な原因」を解説していきます。
エンジニアへの認知度が低い
どれだけ魅力的な環境や待遇を用意していても、エンジニアに認知されていなければ応募にはつながりません。
特に、スタートアップや知名度の低い企業は、そもそもターゲット層に情報が届いていないケースが多いです。
「求人を出せば見てもらえる」という考えでは、なかなか応募者が集まらないのが現実です。
採用ターゲットが明確でない
「即戦力がほしい」「ポテンシャル採用も考えたい」と、求める人物像が曖昧なまま採用活動を進めていませんか?
ターゲットが明確でないと、求人の打ち出し方もぼやけてしまい、エンジニア側も「自分に合ったポジションなのか」が分からず、応募をためらってしまいます。
また、面接時の評価基準もブレやすく、結果として「なんとなく良さそうだから採用」「求める人材と少し違うが妥協して採用」といった判断が増え、ミスマッチが発生しやすくなります。
採用担当者のエンジニアリングへの知識の欠如
採用担当者がエンジニアリングに関する知識を持っていないと、求人票の内容が的外れになったり、面接で適切な質問ができなかったりすることがあります。
エンジニア側からすると、「技術の話が通じない」「採用担当者が求めているスキルが分からない」と感じ、興味を失ってしまうことも。
採用担当者のエンジニアリングへの知識が欠如していることは、採用活動の過程でミスマッチが生じやすくなる要因のひとつです。
開示している情報が少ない
エンジニアにとって、使用する技術や開発フロー、具体的な職場環境や福利厚生は非常に重要なポイントです。
しかし、求人票や採用ページに、そういったエンジニアが欲しい情報がほとんど載っていない企業も多く、結果として応募を逃してしまいます。
「どんな技術を使っているのか」「どんなチームで働くのか」「リモートワークは可能なのか」といった情報が不足していると、エンジニアは判断材料を得られず、別の企業を選んでしまうこともあります。
エンジニアにとって魅力的な求人票になっていない
エンジニア向けの求人票は、単なる業務内容や募集要項の羅列ではなく、「この会社で働く魅力」を伝えることが重要です。
しかし、よくある求人票は「スキル要件」「給与」「福利厚生」の情報しかなく、エンジニアに響かないケースが少なくありません。
「この会社で働くと、どんな成長ができるのか」「どんな課題にチャレンジできるのか」など、エンジニアがワクワクするような要素がなければ、他の求人と比較されて埋もれてしまいます。
企業とエンジニア間で条件面にギャップがある
企業が提示する条件と、エンジニアが求める条件にギャップがあると、選考が進んでも内定辞退につながりやすくなります。
例えば、エンジニアは「リモートワークやフレックスタイム」を希望しているのに、企業は「出社必須」としている場合、ミスマッチが起こります。
企業側が提示する給与や待遇、業務内容、働き方の条件と、エンジニアが求めるものに差があると、応募が集まりにくくなり、せっかく内定を出しても辞退されるケースが増えてしまいます。
採用選考フローが明確でない
「面接は何回あるのか」「技術試験はあるのか」「どれくらいの期間で合否が出るのか」といった選考フローが曖昧だと、応募者の不安が募ります。
特に、他社と並行して選考を進めているエンジニアにとって、選考フローの不透明さは大きなストレスになります。
「この会社のプロセスがよく分からないから、選考を辞退しよう」と思われてしまうこともあります。
採用選考の期間が長すぎる
選考に時間をかけすぎると、エンジニアは待っている間に他社のオファーを受け、そちらを選んでしまうことがあります。
特に、優秀なエンジニアほど複数の企業から声がかかっているため、選考期間が長い企業はどうしても不利になります。
「一次面接から最終面接まで1ヶ月以上かかる」といったケースでは、競争に負けてしまう可能性が高くなります。
応募者のスキル評価の基準が曖昧
「このスキルがある人を採用したい」と言いながら、実際の選考で評価基準が統一されていないと、せっかくの応募者を取りこぼしてしまいます。
また、採用基準が曖昧だと、「この人は何となく合わなさそう」という主観的な判断で不採用になるケースも出てきます。
結果として、優秀なエンジニアを逃してしまい、採用が難しくなってしまいます。
優秀なエンジニアを採用するためにやるべき17の対策
競争の激しいエンジニア採用市場では、企業側がしっかりと戦略を立て、魅力的な採用活動を行うことが重要です。
採用の計画段階から、認知・応募、内定・入社、そして定着まで、それぞれのフェーズで適切な施策を講じることで、採用成功率を高めることができます。
ここでは、エンジニア採用を成功させるために企業が実践すべき具体的な対策を、以下の4つのフェーズに分けて解説します。
- 採用の計画段階でやるべき6つの対策
- 認知〜応募段階でやるべき6つの対策
- 内定〜入社段階でやるべき2つの対策
- 入社後にやるべき3つの対策
採用の計画段階でやるべき6つの対策
エンジニア採用を成功させるためには、計画段階での準備が非常に重要です。
場当たり的な採用活動では、優秀なエンジニアを獲得することは難しく、結果として採用コストの無駄につながることもあります。
ここでは、採用計画の段階で押さえておくべき6つの対策について解説します。
競合調査と市場分析を行う
競合企業の採用状況や市場の動向を分析し、自社の採用戦略を最適化しましょう。
エンジニアの採用市場は常に変化しており、競合他社がどのような条件で採用しているのかを把握することが重要です。
また、求職者のニーズや市場全体の傾向を理解することで、効果的な採用施策を打ち出すことができます。
例えば、競合他社がリモートワークや副業を許可している場合、自社も柔軟な働き方を採用条件に加えることで、より多くのエンジニアに興味を持ってもらえます。
また、最新のエンジニア向け給与水準を調査し、適正なオファーを提示できるようにすることも重要です。
市場の動向や競合の採用手法を理解し、それを基に自社の採用方針を調整することで、より効果的な採用活動が可能になります。
自社の魅力や特徴を整理する
自社ならではの魅力や強みを明確にし、エンジニアに伝わるように整理しましょう。
多くの企業がエンジニア採用に力を入れる中で、選ばれる企業になるためには「なぜこの会社で働くべきなのか」を明確にすることが重要です。
エンジニアにとって魅力的なポイントを整理し、採用活動全体に一貫性を持たせることで、応募意欲を高めることができます。
例えば、「最新の技術を積極的に導入している」「エンジニアの裁量が大きい」「技術コミュニティとの交流が盛ん」など、エンジニアが関心を持つ要素を整理します。
これを採用サイトや求人票に反映することで、より効果的な訴求が可能になります。
他社との差別化を図るために、自社の魅力を明確にし、それを採用活動に活かしていきましょう。
採用ターゲットを明確にする
どのようなスキルや経験を持つエンジニアを採用したいのか、ターゲットを明確にしましょう。
ターゲットが曖昧なままだと、採用活動の方向性が定まらず、効果的なアプローチができません。
また、適切な候補者に適切なメッセージを届けることが難しくなります。
例えば、「フロントエンドエンジニア」「バックエンドエンジニア」「ネットワークエンジニア」など、職種を細かく定義し、それぞれに求めるスキルや経験年数を明確にします。
さらに「リモートワーク希望者向け」なのか、「オフィス勤務が前提」なのかといった働き方の要素も考慮すると、よりターゲットを明確にできます。
ターゲットを明確にすることで、効果的な採用施策を打ち出し、適切な人材を引き寄せることができます。
採用要件を明確にする
「このスキルがあれば採用」「これが不足している場合はNG」といった採用要件を明確にしましょう。
採用要件が不明確なままだと、選考の基準がブレてしまい、適切な人材を見極めることが難しくなります。
また、エンジニア側も自分が応募資格を満たしているのか分からず、応募をためらってしまうことがあります。
例えば、「Reactでの開発経験3年以上」「AWSの運用経験がある」といった具体的なスキル要件を設定します。
また、「未経験でもポテンシャル採用可」なのか「即戦力のみを募集している」のかを明確にすることで、適切な応募者を集めることができます。
採用要件を明確にすることで、ミスマッチを防ぎ、スムーズな採用活動を進めることができます。
採用戦略を策定する
計画的に採用を進めるために、具体的な採用戦略を立てましょう。
行き当たりばったりの採用活動では、思うように成果が出ません。
どの採用手法を活用し、どのタイミングでどのようなアクションを取るのかを明確にすることで、効率的に採用を進めることができます。
例えば、「1月〜3月は新卒採用に注力し、4月〜6月は中途採用にフォーカスする」「SNSやエンジニア向けのコミュニティを活用し、ターゲットに直接アプローチする」といった戦略を立てます。
また、ダイレクトリクルーティング、リファラル採用、求人広告など、複数の採用手法を組み合わせることで、より効果的な採用が可能になります。
明確な戦略を持つことで、効率的に採用活動を進め、優秀なエンジニアを確保しやすくなります。
予算とリソースを確保する
採用活動に必要な予算とリソースを事前に確保しておきましょう。
エンジニア採用には、求人広告の費用や採用担当者の工数、選考プロセスにかかるコストなど、さまざまなリソースが必要です。
十分な準備がないと、途中で採用活動が行き詰まってしまう可能性があります。
例えば、「年間の採用予算を300万円確保し、求人媒体・リクルーター・リファラル採用に振り分ける」といった計画を立てることで、スムーズに採用を進めることができます。
また、採用チームの体制を整え、必要に応じてエンジニアも面接官として参加できるようにすることも重要です。
採用の成功には、十分な予算と人員の確保が不可欠です。
事前に準備を整え、スムーズな採用活動を実現しましょう。
認知〜応募段階でやるべき6つの対策
優秀なエンジニアを採用するためには、まず企業の存在を知ってもらい、興味を持ってもらうことが不可欠です。
「どんな技術に取り組んでいるのか?」「どんな環境で働けるのか?」といった情報を発信し、求職者にとって魅力的な企業であることを伝える必要があります。
ここでは、認知度を高め、応募につなげるための6つの具体的な対策を紹介します。
企業の採用ブランディングを強化する
採用ブランディングとは、「企業が採用力強化を目的として、求職者に対して自社をブランディングすること」です。
優秀なエンジニアは、自分が成長できる環境や魅力的な企業文化を求めており、単に給与や条件だけで転職先を決めるわけではありません。
そのため、企業側が「どんな技術に取り組んでいるのか」「どのようなエンジニアが活躍しているのか」「働きやすい環境が整っているのか」などを積極的に発信し、認知度を高めることが必要です。
しかし、効果的な採用ブランディングを実践するには、適切な発信手法やエンジニアとの接点を持つ場が不可欠です。
そこでおすすめなのが、採用ブランディング支援サービス「TECH PLAY Branding」 です。
TECH PLAY Brandingは、エンジニア向けのイベントやコミュニティ運営を通じて、企業の技術力やカルチャーをアピールし、採用につなげるためのサービスです。
特に、採用サイトや技術ブログ、SNS、イベントなどを活用し、企業の強みや開発環境、カルチャーを継続的に発信することは、エンジニアからの共感を得る上で非常に有効です。
TECH PLAY Brandingを活用すれば、企業とエンジニアが直接つながる場を作ることができ、より深い関係を築くことができます。
このように採用ブランディングを強化することで、「この企業で働きたい」と思うエンジニアが増え、結果として応募数の増加や選考辞退率の低下につながります。
採用チャネルを増やす
複数の採用チャネルで採用活動を行うと、エンジニアとの接点を増やせます。
応募者が集まれば母集団を形成でき、自社が求めるエンジニアを採用しやすくなります。
例えば、下記のような施策が考えられます。
- 契約するエージェントの数を増やす
- スカウト媒体を増やす
- リファラル採用や広告の活用を新たに開始する
など、さまざまなチャネルを利用しエンジニアとの接点を増やし、カバーできる範囲を広げることがおすすめです。
魅力的な求人票を作成する
求人票はエンジニアが最初に目にする企業の顔です。
魅力的な求人票を作ることで、応募率を大きく向上させることができます。
特に、仕事内容や使用する技術やプログラミング言語、開発プロセスを明確にし、求めるスキルと期待する役割を具体的に記載することが重要です。
例えば、「最新の技術を積極的に導入している」「エンジニアの裁量が大きい」「リモートワーク可能」など、エンジニアにとって魅力的なポイントを分かりやすく伝えましょう。
曖昧な表現を避け、リアルな業務内容を示すことで、適切なマッチングが実現し、応募のハードルが下がります。
スカウトメールの質を向上させる
エンジニアへのスカウトメールは、テンプレートを流用しただけの内容ではほとんど読まれません。
個別にカスタマイズし、相手のスキルや経歴に合わせたメッセージを送ることで、返信率を大幅に向上させることができます。
例えば、「あなたのGitHubのプロジェクトを拝見し、非常に興味を持ちました」「過去の技術ブログの記事を読み、ぜひお話を伺いたいです」といった具体的な言及をすることで、候補者に誠意が伝わります。
丁寧でパーソナライズされたスカウトメールを送ることで、より多くのエンジニアと接点を持つことが可能になります。
応募のハードルを下げる
応募時の手続きが複雑だと、それだけで候補者が離脱してしまう可能性があります。
スムーズに応募できる仕組みを整え、気軽にエントリーできる環境を作ることが重要です。
例えば、応募フォームを短縮し、「履歴書不要」「カジュアル面談OK」などの柔軟な対応を取り入れることで、応募の心理的ハードルを下げることができます。
また、SNS経由での応募や、チャットツールを活用したやり取りを導入することで、より多くのエンジニアと接触する機会を増やせます。
選考プロセスをスピーディーに進める
選考プロセスのスピードは、エンジニア採用において非常に重要な要素です。
選考が長引くと、応募者のモチベーションが下がり、他社に流れてしまうリスクが高まります。
特に優秀なエンジニアは複数の企業からオファーを受けることが多く、迅速な対応ができない企業は採用競争に負けてしまいます。
スムーズな選考のために、具体的に意識するべきことは以下の3つです。
- 書類選考や面接後の合否連絡を速やかに実施する
- 面接のスケジュールは即座に調整する
- 内定後のプロセスを明確にし、迅速に対応する
「採用はスピードが命」と言われるほど、選考の速さは採用成功に直結します。
企業側の都合だけでなく、エンジニアの視点に立ち、迅速かつスムーズな選考フローを整えることが、優秀な人材を逃さないための重要なポイントです。
内定〜入社段階でやるべき2つの対策
エンジニア採用に成功しても、内定を出した後に辞退されてしまったり、入社までのフォローが不十分でスムーズに業務を開始できなかったりすると、採用活動の成果が半減してしまいます。
特に、内定から入社までの期間は、候補者が他社のオファーを検討したり、現職と比較して迷ったりするタイミングでもあるため、このフェーズで適切な対応をすることで、内定辞退のリスクを減らし、入社後の定着率を高めることができます。
ここでは、企業が内定〜入社段階で実践すべき2つの対策について解説します。
内定者フォロー面談により不安を取り除く
内定を出した後も、候補者の不安を解消し、入社意欲を高めるためのフォローが重要です。
特に、他社からのオファーと比較検討しているケースも多いため、積極的なコミュニケーションを行うことで辞退を防げます。
例えば、「現場エンジニアとの座談会を開催」「オフィス見学を実施」「入社前の勉強会への参加を促す」といった施策を取り入れることで、入社後のイメージを具体化し、安心感を与えることができます。
スムーズに業務に取りかかれるよう支援する
入社後すぐに活躍できる環境を整えることで、新入社員の定着率を向上させることができます。
業務用PCの準備、アカウント発行、オンボーディング資料の提供など、初日からスムーズに業務を開始できる仕組みを整えましょう。
例えば、「メンター制度を導入し、入社1ヶ月間はフォロー体制を強化する」「入社前に学習コンテンツを提供し、業務理解を深める」といった施策が有効です。
入社後にやるべき3つの対策
優秀なエンジニアを採用できても、入社後のフォローが不十分だと早期離職につながってしまいます。
特に、エンジニアはスキルアップの機会や働きやすい環境を求める傾向が強く、これらが不足しているとモチベーションが低下し、転職を考えてしまうこともあります。
エンジニアが長く活躍できるよう、企業が入社後に取り組むべき3つの重要な対策を紹介します。
エンジニアのスキルアップ支援
エンジニアの成長意欲を満たすために、継続的なスキルアップの機会を提供することが重要です。
技術の進化が早い業界では、学び続けられる環境があるかどうかが定着率に影響します。
例えば、「資格取得支援制度」「カンファレンス参加補助」「社内勉強会の実施」などを導入することで、エンジニアのモチベーション向上につながります。
適切な評価の実施
エンジニアが適正に評価されていると感じられる環境を整えることで、モチベーションを維持しやすくなります。
成果だけでなく、技術力の向上やチームへの貢献度も評価する制度を設けましょう。
例えば、「コードレビューの質を評価基準に加える」「定期的なフィードバックを実施する」といった取り組みが有効です。
働きやすい環境の整備
エンジニアが集中して働ける環境を提供することで、定着率を高めることができます。
例えば、「フレックスタイム制度」「リモートワークの推進」「エンジニア向けの設備投資」など、働きやすさを向上させる施策を導入することが効果的です。
エンジニア採用の参考になる成功事例15選
採用市場が厳しい中でも、効果的な施策を実施し、エンジニア採用を成功させている企業も存在します。
本章では、エンジニア採用に成功している企業の具体的な事例を15個紹介します。
ブランディングの強化、採用フローの工夫、魅力的なオファーの提示など、それぞれの企業がどのような工夫をしているのかを詳しく解説します。
自社の採用活動に活かせるヒントを見つけてください。
マッチングを重視したエンジニアの採用事例2選
企業と応募者のマッチングを重視した、エンジニアの採用事例を2つ紹介します。
事例1.イオンドットコム株式会社
イオンドットコム株式会社は、新組織を作るにあたり、応募者のマッチング度を重視しました。
採用活動ではスキルはもちろんのこと、時間をかけて人間性を判断しています。
例えば面接では、応募者のコミュニケーション能力と志望動機をチェックし、事前に実施した適性検査をもとに質問する内容を変えました。
結果として、採用した人から「こんなに働きやすいところはない」といわれるほど、マッチングに成功しています。
事例2.BASE株式会社
BASE株式会社は、スクラム採用を選択しました。
スクラム採用とは、現場が主体となって採用活動を推進する手法です。
現場のエンジニアにスクラム採用のメリットを説明して協力を得た結果、採用活動を強化できました。
また、従業員同士の連帯感も生まれ、チームとしての力も向上しています。
採用広報に注力したエンジニアの採用事例6選
採用広報も採用活動に効果的です。
採用広報に注力した企業の事例を6つ紹介します。
事例3.トヨタ自動車株式会社
トヨタ自動車株式会社は、ソフトウェアファーストなモノづくりのため、優秀なエンジニアを求めていました。
しかし、自動車産業がエンジニアを必要としている状況があまり認知されていませんでした。
同社は、TECH PLAYでのイベントを通じて技術や課題の認知に努めています。
1回のイベントにあたり、800人程度を集客でき、採用活動を強化できました。
また、同社は、採用サイトにTECH PLAYイベントアーカイブを掲載中です。
アーカイブでは、TECH PLAYのウェビナー動画や、具体的な開発事例を視聴できます。
※参考:トヨタ自動車がソフトウェアエンジニア採用を強化 採用ブランディング成功の秘訣とは
※参考:トヨタ自動車㈱ のイベント・技術情報|TECH PLAY
事例4. 株式会社NTTデータ
1988年の設立以来、日本のシステムインテグレーション業界をけん引し、今なお国内トップSIerとして業界をリードする株式会社NTTデータ。
「2023年卒の就活生が選ぶIT業界新卒就職人気企業ランキング」(楽天「みん就」発表)では1位を獲得するほどの人気企業ですが、一方で経験者採用には「事業の認知度不足」という課題も抱えていました。
社会的価値が高く魅力的な業務の認知度を上げるべく、NTTデータの中でも製造業・流通業・サービス業等顧客を対象とする法人分野では、2021年より採用ブランディングを実施。
TECH PLAYも導入していただき、今まさに効果を実感しているとのことです。
※参考:NTTデータの“真の魅力”を継続的に届ける 優秀な人材確保につながった採用ブランディングの手法とは
事例5. アバナード株式会社
アクセンチュアとマイクロソフトの戦略的合弁企業として2000年に米国でスタートしたアバナード株式会社。
マイクロソフトのテクノロジーとアクセンチュアのビジネスの知見を生かし、コンサルティングからシステムの設計・開発・導入・保守までワンストップで提供しています。
IT業界でも一目置かれるグローバル企業です。
技術発信の場としてTECH PLAYもご利用いただいていますが、そのイベントは、「IoTの力でビールを醸造してみた」「AI判定型ビリビリクイズマシンを作ってみた」など、個性的なものが多いのも特徴。
現在採用も急拡大する中、斬新な技術発信に力を入れ、採用につなげています。
※参考:「テックビール」「ビリビリクイズマシン」!? アバナードが斬新な技術発信に力を入れる理由
事例6. 株式会社AGEST
ソフトウェアのQA専門の会社として、ソフトウェアテスト、システムインテグレーション、セキュリティ分野における課題解決をワンストップで提供する株式会社AGEST(以下AGEST)。
技術広報の一環としてTECH PLAYも導入いただいております。
AGESTがTECH PLAYを導入いただいた大きな理由には、ソフトウェア開発におけるQAの重要性を広めたいという想いがありました。
ソフトウェアにおけるQAの重要度は高まっているにも関わらず、日本国内全体でQAに対する認知度・関心度が低い。
採用を見据えたうえで、まずはこの価値観そのものを変えていく必要があるという課題を抱えていた同社。
テックカンパニーとしてQAの認知度向上を最大の目的としつつ、「QAエンジニア」という職業をキャリアの選択肢をブランディングする効果を狙ってTECH PLAYでウェビナーを実施。
これまで開催した全ウェビナーで定員を当初の予定より増員するほど集客は好調。計4回のイベントで980名増員という結果に。集まる学生も意識の高い方が増えているそうです。
※参考:「QAの価値観を変える」 TECH PLAYを駆使したAGESTの挑戦
事例7.株式会社ココナラ
株式会社ココナラは、応募者の少なさと、採用担当者が少ないことから広報活動に工数をかけられない状況が課題となっていました。
採用活動の成果を高めるべく、同社は少ない工数で集客力が見込めるSNS広告に注力しました。
テレビCM放映期間とSNS広告を打つタイミングを合わせたところ、効果的に自社の魅力をターゲットにアピールできました。
募集ページのPVが10倍以上に増え、幅広い職種のエンジニアを採用できています。
※参考:一度の広告掲載で6名の採用に成功。 ココナラが考えるWantedly広告オプション活用術|株式会社ココナラ
事例8.株式会社アンドパッド
株式会社アンドパッドは、企業のパーパス(意図・目的)への共感を重視して、採用活動に取り組みました。
例えば求人サイトのWantedlyでは、エンジニアのインタビューを発信しています。
このようにエンジニア採用サイト、技術ブログなどを利用しての外部発信に加えて、社内の技術組織からの発信も増やし、応募者を増やしました。
また、エンジニア領域は使われる用語が難しく、ある程度知識のある担当者でなければ、採用活動がスムーズに進みません。
同社はエンジニアに特化した採用部門を設置し、採用活動の質や効率を向上させました。
求人サイトによるエンジニアの採用事例2選
さまざまな求人サイトを活用したエンジニアの採用事例を2つ紹介します。
事例9.株式会社モンスターラボ
株式会社モンスターラボは、求人サイトWantedlyを活用し、約1年半で正社員のべ50名を採用しました。
同社は、具体的な内容や関心の高いキーワードを盛り込んで、求人情報を掲載しています。
掲載数に上限はないため、iOSエンジニアなど具体的な職種を指定し、複数の募集を掲載しました。
さらに、募集を繰り返すなかで試行錯誤することで、ターゲットに響く募集のコツを理解できました。
※参考:1年半で60名以上の「会社を一緒につくる仲間」に出会えた!Wantedly運用ノウハウ | SELECK [セレック]
事例10.株式会社ベリサーブ
株式会社ベリサーブは、ハイクラス人材のポテンシャルを見極め、入社動機を高められる採用フローを構築しています。
同社は求人サイトのdodaと連携し、必要なポジションや求める人物像を、応募者に明確に伝えました。
また、事業トップが自らカジュアル面談を実施し、応募者に合わせて、採用フローをカスタマイズしています。
同社はハイクラス人材の獲得に成功し、2022年の1Qから3Qにかけ、内定承諾率が44%から69%に上昇しました。
加えて、40日程度かかっていた採用フローが1か月程度まで短縮できました。
※参考:株式会社ベリサーブ「経験豊富なITエンジニアの獲得に成功」|doda中途採用をお考えの法人様へ
ダイレクトリクルーティングによるエンジニアの採用事例3選
企業から応募者にアプローチする、ダイレクトリクルーティングを活用した採用事例を3つ紹介します。
事例11.ラクスル株式会社
ラクスル株式会社は、エンジニア出身のスカウトが在籍する、ダイレクトリクルーティングサービスを選びました。
スタッフの経歴にこだわった理由は、エンジニアに響くスカウトメールを送るためです。
他にも同社は、スカウト送信のコツやノウハウを共有し合い、集中してスカウトメールを送る時間を設けるなどして、ダイレクトリクルーティングを成功させています。
事例12.株式会社スリーシェイク
株式会社スリーシェイクは、スカウト返信率の低さが課題でした。
同社は、現場のエンジニアの協力を得て、スカウトメールの作成にも加わってもらいました。
学習環境やサポート体制など、ターゲットが重視するポイントを押さえたスカウトメールを送ることで、スカウト経由の採用が増えました。
事例13.マネーフォワード株式会社
マネーフォワード株式会社は、自社にマッチする人材の採用が課題でした。
同社は、現場のエンジニアを巻き込みながら採用活動に取り組みました。
現場のエンジニアの負担を減らすため、事前に対応してもらう内容をすり合わせています。
さらに、採用活動の目的を共有するなどして現場と信頼関係を構築しました。
同社はターゲットが興味を持ちそうなセミナーやイベントに加え、自社を知ってもらう採用広報にも注力しています。
ダイレクトリクルーティングを含むさまざまな施策が相乗効果を発揮して、応募者を増やすことができました。
リファラル採用によるエンジニアの採用事例3選
従業員の人脈を活用したリファラル採用によるエンジニアの採用事例を3つ紹介します。
従業員の協力を得て、リファラル採用の成果を高めましょう。
事例14.freee株式会社
freee株式会社は「リファラルでの採用者には、優秀な人が多い」と考えた結果、従業員が採用活動に協力しやすい体制を構築しました。
同社は、ターゲットの人物像を明確にして、定期的に全社に発信しています。
また、スカウトするときにターゲットに渡せるように、紙の紹介カードも作成・配布しました。
周年パーティーで、リファラル採用の協力者を表彰する仕組みも整えています。
このように全社を挙げて体制を整えた結果、リファラル採用の比率を大幅に増やせました。
事例15.株式会社メルカリ
株式会社メルカリは、「求人サイトからの応募者が、自社にマッチするとは限らない」と考えています。
同社は、ダイレクトリクルーティングツールにLinkedInを採用しました。
LinkedInは世界規模のビジネス特化型SNSです。
LinkedInの登録者には豊富なキャリアを持つ人や、英語が堪能な人が少なくありません。
同社はLinkedInの登録者をミートアップイベントに招待し、選考に進んでもらうようアプローチをかけました。
また、採用会食のように、従業員がリファラル採用に取り組みやすい体制も整備しています。
株式会社メルカリが取り組む、エンジニア採用に向けた技術広報について徹底解説した動画がこちらです。
興味のある方はぜひご覧ください。
事例16.富士通株式会社
富士通株式会社は、ビジネス拡大に向け専門性の高い優秀な人材を多数必要としていました。
同社は、3.3万人もの信頼する従業員の「つながり」を活かして、リファラル採用を導入しました。
リファラル採用の成果を高めるべく導入された施策が、「GoToリファラルキャンペーン」です。
キャンペーンは紹介者に1万円のギフト券がプレゼントされる、総額200万円の大がかりなものでした。
同社は、2023年1月時点で累計80名をリファラル採用で獲得し、退職者数は0名です。
また、以前と比較すると、採用活動費を累計で1.2億円削減できているそうです。
※参考:社員3.3万人の人脈を活用!DX企業・富士通が取り組むリファラル採用の秘訣とは |HR NOTE
従来の採用チャネルでのエンジニア採用が難しいなら「TECH PLAY Branding」がおすすめ
従来の採用チャネルだけではエンジニア採用に限界を感じているという企業におすすめなのが、エンジニア向け採用ブランディングサービス「TECH PLAY Branding」 です。
「TECH PLAY Branding」はパーソルイノベーション株式会社が運営する、28万人以上のエンジニア・デジタル人材にアプローチができる採用支援サービスです。
エンジニア採用に詳しい専門メンバーが、採用戦略の立案からエンジニア向けイベントの企画・運営までを支援します。
自社の技術力や開発環境を直接アピールできるイベントを企画・運営しており、エンジニアとの接点を増やし、興味を持ってもらいやすくなります。
単なる採用活動ではなく、エンジニアにとって魅力的な企業として認知されることで、長期的な採用成功につながります。
イベントだけでなく、TECH PLAYのプラットフォームを活用し、エンジニアに向けた情報発信ができるため、興味を持った層にダイレクトにアプローチできます。
従来の採用手法に限界を感じているなら、TECH PLAY Brandingの導入をぜひ活用を検討してみてください!
まとめ
エンジニア採用が難しいと感じる企業は多く、その背景には人材不足だけでなく、採用市場の変化や企業側の課題など、さまざまな要因が関係しています。
応募が集まらない、内定を辞退される、採用してもすぐに離職してしまうといった悩みを抱える企業も少なくありません。
しかし、適切な採用戦略を立て、各フェーズで効果的な施策を実施すれば、優秀なエンジニアと出会い、採用成功率を高めることができます。
市場や競合を分析し、自社の魅力を発信すること、採用チャネルを広げ、応募のハードルを下げること、そして入社後もエンジニアが成長しやすい環境を整えることが重要です。
エンジニア採用は年々難しくなっていますが、適切な対策を講じれば、企業にとって必要な人材を確保することは十分に可能です。
本記事を参考に、自社の採用活動を見直し、成功に向けた一歩を踏み出してみてください。

この記事を書いた人
TECH PLAY BUSINESS
パーソルイノベーション株式会社が運営するTECH PLAY。約23万人※のテクノロジー人材を会員にもつITイベント情報サービスの運営、テクノロジー関連イベントの企画立案、法人向けDX人材・エンジニア育成支援サービスです。テクノロジー人材のエンパワーメントと企業のDX化の成功をサポートします。※2023年5月時点
よく読まれている記事
\「3分でわかるTECH PLAY」資料ダウンロード/
事例を交えて独自のソリューションをご紹介します。