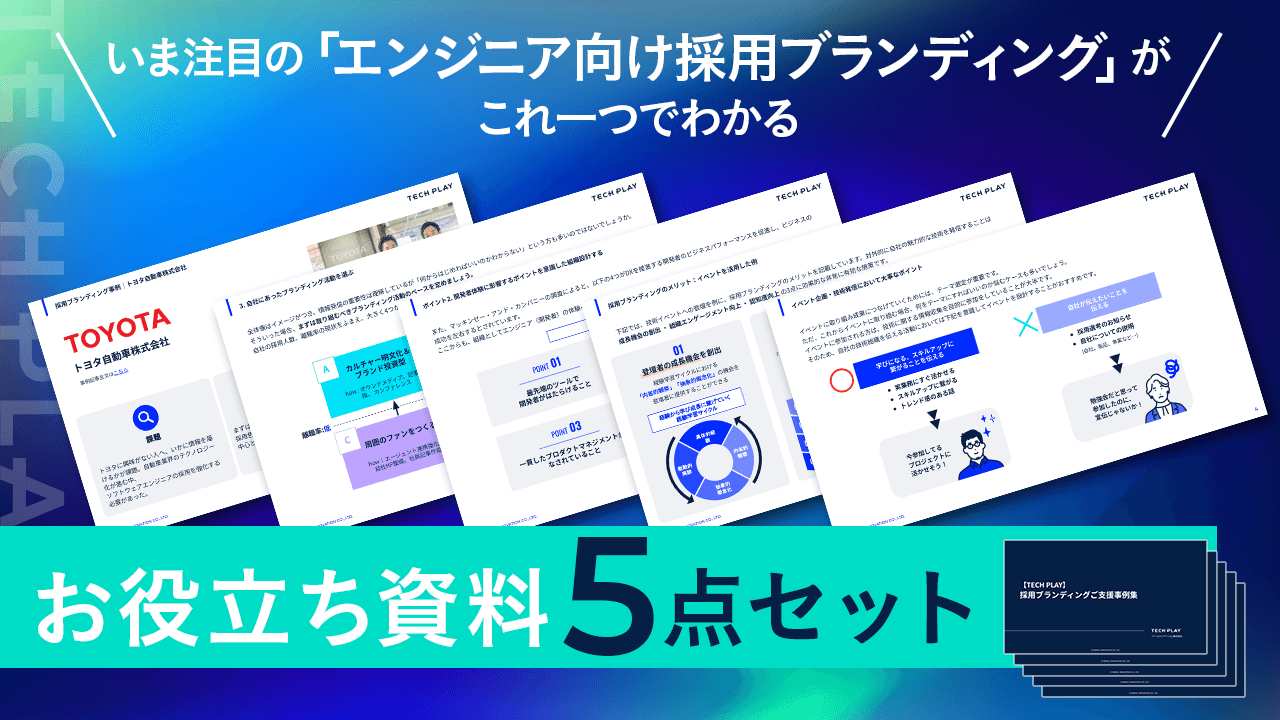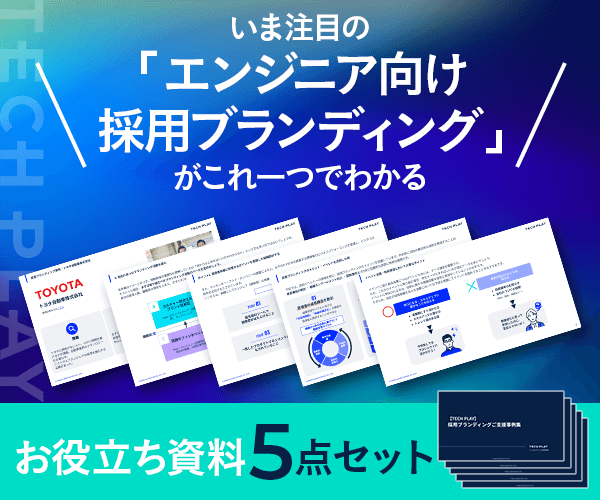エンジニアの中途採用を成功させるには?5つのポイントを解説!
近年、エンジニアの需要が高まる一方で、優秀な人材の確保がますます難しくなっています。
特に即戦力となる中途エンジニアの採用では、競争が激しく、採用活動に課題を感じている企業も多いのではないでしょうか。
本記事では、「求人を出してもなかなか応募が来ない…」「採用できてもすぐに辞めてしまう…」といった悩みを抱えている企業のために、エンジニアの中途採用を成功させるための5つの重要なポイントを解説します。
求職者の目線を理解し、エンジニアの中途採用を成功させる具体的な8つの施策についても具体的に紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
中途採用に応募するエンジニアが抱える不安とは?
新卒採用とは異なり、中途採用に応募するエンジニアは前職での経験がある分、さまざまなバックグラウンドを抱えています。
そのため、中途採用の成功を実現させるためには、転職を希望する、もしくは将来的に転職を希望する可能性がある現役エンジニアの不満を知ることからスタートする必要があります。
転職サービス「doda」が実施した「ITエンジニアの関心事とキャリアに関する調査」によると、現役エンジニアは、業務で以下のような不安を抱えています(N=1,500)。
また、同調査によると、実際に転職したエンジニアの転職理由は以下のとおりです(同調査による)。
これらのデータを見ると、在籍中のエンジニアが抱えている不安と、実際に転職をしたエンジニアが転職に至った理由には共通点が多いことが分かります。
具体的には、エンジニアは大きく分けて以下の4つのような不安を抱えています。
- 給与に対する不安
- スキルやキャリア形成に関する不安
- 労働量が多く休暇が少ないことに関する不安
- 勤務先の会社の経営状態に関する不安
それぞれの不安について、詳しく解説します。
給与に対する不安
エンジニアが転職を考える理由の中でも、「給与への不安」は特に多く挙げられる理由の一つです。
エンジニアは専門性の高い職種でありながら、業務内容やスキルに見合った報酬が得られていないと感じると、不満が蓄積しやすくなります。
特に、同じ業界や職種であっても、企業によって給与水準が大きく異なることが多く、「自分の市場価値はもっと高いのではないか」と疑問を持つエンジニアは少なくありません。
求人情報や転職エージェントから提示される他社の給与額を知ることで、現在の待遇との差を強く意識するようになります。
また、昇給の機会が限られていたり、評価制度が不透明だったりすると、「このまま今の会社にいても給料は上がらないのではないか」という不安が生まれます。
加えて、最新技術を学び、スキルを磨いても、給与に反映されない場合も不満につながります。
特に、経験を積むことで価値が上がるはずの職種にもかかわらず、新卒時から大きな昇給がない場合、「どれだけ頑張っても評価されないのではないか」と感じることもあります。
給与の問題は、エンジニアにとって生活に直結するだけでなく、モチベーションやキャリア選択にも大きな影響を与える重要な要素となっています。
スキルやキャリア形成に関する不安
エンジニアにとって、スキルアップの機会が限られていたり、将来的なキャリアが見えなかったりすることは、大きな不安要素となります。
技術の進化が速い業界だからこそ、「今の会社でこのまま働き続けて、成長できるのだろうか?」という悩みを抱えることが少なくありません。
特に、業務内容が同じ技術を使った作業の繰り返しで、新しい技術に触れる機会が少なかったりすると、スキルが停滞してしまうという危機感が生まれます。
例えば、長年同じシステムの保守運用ばかりを担当していると、新しい技術トレンドに適応する機会がなくなり、「このままでは市場価値が下がってしまうのではないか」と感じることがあります。
また、学習のための時間や支援制度がない企業では、自主的に勉強を続けることが難しく、結果的にキャリアの選択肢が狭まることを恐れるエンジニアも多いです。
さらに、キャリアパスが不透明で、「このまま働いても昇進の機会があるのか分からない」といった悩みもあります。
エンジニアのキャリアには、大きく分けて技術を突き詰めるスペシャリストの道と、マネジメント職に進む道がありますが、どちらの選択肢も明確に示されていない企業では、「この会社での自分の未来が見えない」と感じることが多くなります。
その結果、より明確なキャリアプランが描ける企業への転職を考えるようになります。
労働量が多く休暇が少ないことに関する不安
エンジニアの仕事は、納期やシステムトラブル対応などの影響で長時間労働になりやすい傾向があります。
特に、プロジェクトの進行管理が適切でない企業では、過剰な負担がかかり、ワークライフバランスが崩れることが多くなります。
「休日でも急な対応を求められる」「残業が常態化している」「有給休暇が取りづらい」といった状況に直面すると、働き続けることに不安を感じるようになります。
特に、納期が厳しいプロジェクトでは、終電近くまで働くことが当たり前になっていたり、休日返上で対応しなければならないこともあります。
その結果、プライベートの時間が削られ、心身の負担が大きくなります。「このままでは健康を損ねてしまうのではないか」と感じるエンジニアも多く、疲労が蓄積すると仕事へのモチベーションが低下し、転職を考えるきっかけになります。
また、システム障害やトラブル対応が頻繁に発生する環境では、精神的なストレスが大きくなりやすいです。
特に小規模な企業や人員が不足している職場では、常に少人数で業務を回しているため、特定のエンジニアに負担が集中しやすくなります。
十分な休息が取れない状況が続くと、疲労やストレスが限界に達し、長く働き続けることに強い不安を感じるエンジニアは少なくありません。
勤務先の会社の経営状態に関する不安
エンジニアが働く環境は、企業の経営状態によって大きく左右されます。
会社の売上や資金繰りが不安定な場合、将来的なキャリアの見通しが立たなくなり、不安を感じるようになります。
「この会社は今後も成長できるのか」「突然リストラされたり、給与カットされたりするリスクはないか」といった疑問を持つようになると、より安定した企業への転職を検討し始めます。
特に、企業の経営方針が頻繁に変わる場合や、リーダーシップが一貫していない場合、将来への信頼感が薄れてしまいます。
例えば、経営陣の意思決定が不透明だったり、短期間で方針が大きく変わったりすると、「この会社についていって大丈夫なのか」と不安になることがあります。
また、新規事業の立ち上げや投資が相次ぐものの、明確な成果が見えない場合、「経営がうまくいっていないのではないか」と懸念を抱くエンジニアも少なくありません。
加えて、業界全体の成長性にも影響を受けます。
競争が激しい市場では、「この会社は今後生き残れるのか」という疑問が生まれ、より安定した市場に属する企業への転職を検討する人が増えます。
エンジニアは自分のキャリアを長期的に考えるため、経営の不透明さや不安定な業績は、大きな転職理由の一つとなります。
エンジニアの中途採用を成功させるために重要なポイント5選
前章で解説したように、現役エンジニアはさまざまな不安を抱えているため、その不安を解消することが、エンジニアの中途採用を成功させるための鍵となります。
エンジニアが抱えている不安を踏まえた、企業がエンジニアの中途採用を成功させるために重要なポイントは以下の5つです。
- 給与や賃金の評価基準や昇給額などを明確にする
- スキルアップ支援の体制を明確に伝える
- 残業時間や取得できる福利厚生を明確にする
- 自社の取引先や経営状況を明確にする
- 社員のインタビュー記事などを掲載する
それぞれ、詳しく解説します。
給与や賃金の評価基準や昇給額などを明確にする
エンジニアにとって、給与や昇給の基準が不透明な企業は大きな不安要素となります。
自分のスキルや成果がどのように評価され、どのように給与へ反映されるのかが明確でない場合、「どれだけ頑張っても報われないのではないか」と感じてしまうことがあります。
特に、同じ業界内で給与の差が大きいエンジニア職では、転職を検討する際に「他社と比べて自分の待遇は適正なのか?」という視点が強くなります。
そのため、企業側が採用時点で給与や昇給の仕組みを明確に伝えることが重要です。
例えば、「年に1回の評価制度があり、評価結果に応じて昇給額が決定される」「資格取得や特定の技術習得に応じて手当が支給される」といった具体的な制度を示すことで、エンジニアが将来のキャリアを描きやすくなります。
また、実績に基づく昇給例を提示することで、「この会社では努力が正当に評価される」という安心感を与えることができます。
特に、スキルベースで給与が決定されるのか、役職ベースで決定されるのかといった点も明確にすることが求められます。
エンジニアの中には、管理職ではなく技術を極める道を選びたいと考える人も多いため、「スペシャリストでも昇給のチャンスがあるのか」といった点を明示することで、採用時のミスマッチを防ぐことができます。
スキルアップ支援の体制を明確にする
エンジニアは、技術の進化が早い業界で働いているため、常にスキルアップを意識しています。
しかし、企業によっては学習支援制度が整っていなかったり、実務で新しい技術に触れる機会が少なかったりすることがあります。
そのため、転職活動をする際には「この会社で成長できるのか?」という点を重要視するエンジニアが多いです。
企業側は、スキルアップ支援の体制を明確に伝えることで、「成長できる環境が整っている」というアピールができます。
例えば、「月に1回の技術勉強会を実施」「Udemyなどのオンライン学習サービスの利用補助」「資格取得支援制度」などを具体的に示すことで、エンジニアにとって魅力的な職場であることを伝えられます。
また、社内でどのような技術スタックを活用しているのかを明確にし、それに関する学習支援があるのかを伝えることも重要です。
例えば、クラウド技術を多く活用する企業なら、「AWS認定資格の取得支援制度あり」といった具体的な情報を提示することで、興味を持つエンジニアが増える可能性があります。
スキルアップの環境が整っている企業は、優秀なエンジニアを惹きつけるだけでなく、社員の定着率向上にもつながるため、積極的に情報を発信していくことが重要です。
残業時間や取得できる福利厚生を明確にする
エンジニアは、労働環境の良し悪しを重視する傾向が強い職種です。
特に、「長時間労働が常態化しているのではないか」「有給休暇が取得しにくいのではないか」といった点は、転職時に慎重に確認するポイントとなります。
そのため、企業側は残業時間の実態や福利厚生の内容を明確に伝えることが求められます。
例えば、「月の平均残業時間は10時間未満」「フレックスタイム制を導入し、柔軟な働き方が可能」「有給休暇の取得率は80%以上」といった具体的な数値を示すことで、労働環境の良さをアピールできます。
また、リモートワーク制度や副業の可否などもエンジニアにとって重要な情報となるため、明確に伝えることが重要です。
福利厚生についても、単に「各種社会保険完備」と記載するだけではなく、「住宅手当や家賃補助がある」「技術書の購入補助制度がある」など、エンジニアが魅力を感じる内容を詳しく説明することが効果的です。
労働環境が整っていることを具体的に伝えることで、優秀なエンジニアの応募意欲を高めることができます。
自社の取引先や経営状況を明確にする
エンジニアは、自分が働く企業の安定性を重視する傾向があります。
特に、中途採用の場合は「入社後に会社の経営が悪化したらどうしよう」といった不安を抱えることが多いため、企業の経営状況や取引先を明確に伝えることが重要です。
例えば、「直近3年間の売上推移を公開」「取引先は○○業界の大手企業が中心」など、会社の安定性や成長性を示すデータを積極的に開示することで、求職者の安心感を高めることができます。
また、「現在の主力事業と今後の成長戦略」といった情報を説明することで、会社の将来性を伝えることも有効です。
エンジニアは、自分が開発するシステムの影響範囲や社会的意義を重視することも多いため、主要な取引先や導入実績を示すことで、「この会社で働くことが社会にどのような価値を生むのか」を伝えることも重要です。
経営の透明性を確保することで、求職者の信頼を得ることができます。
社員のインタビュー記事などを掲載する
求職者が転職を考える際、実際に働いているエンジニアの声は非常に重要な情報源となります。
企業が公式に発信する情報だけでは伝わりにくい職場の雰囲気や働き方について、現場のエンジニアが語ることで、よりリアルなイメージを伝えることができます。
特に、インタビュー記事では、「なぜこの会社を選んだのか」「入社して良かったと感じる点」「成長を実感したエピソード」などを具体的に掲載することで、求職者に共感を与えることができます。
また、異なる職種やキャリアパスを持つ複数の自社エンジニアの声を紹介することで、多様な働き方ができる環境であることをアピールすることも可能です。
インタビュー記事を通じて、会社の文化や価値観が伝わるようにすることで、求職者とのミスマッチを防ぎ、採用の成功率を高めることができます。
エンジニアの中途採用を成功させる具体的な8つの施策
エンジニアの中途採用は、単に求人を出すだけでは成功しません。
優秀なエンジニアは多くの企業からオファーを受けており、企業側が積極的にアプローチし、魅力を伝える工夫が必要です。
また、採用プロセスの透明性やスピード感、応募者の不安を取り除くためのサポートなど、細かな施策を実施することで、採用成功率を高めることができます。
ここでは、エンジニアの中途採用を成功させるための具体的な8つの施策について解説します。
これらを実践することで、より多くの優秀なエンジニアに興味を持ってもらい、採用後の定着率も向上させることができます。
社内の中途採用したエンジニアにインタビューする
中途採用を検討しているエンジニアにとって、実際に転職したエンジニアの体験談は非常に価値のある情報です。
企業がどのような環境なのか、どのような働き方ができるのか、実際に働いている人の声を通じてリアルに伝えることができます。
特に、転職を考えているエンジニアの多くは「この企業に入社したら本当に自分が成長できるのか」「前職よりも良い環境で働けるのか」といった不安を抱えています。
そのため、インタビューでは「なぜ転職を決意したのか」「入社前に不安だった点は何か」「実際に入社してみてどうだったか」といった内容を詳しく語ってもらうと、求職者の不安を解消する助けになります。
また、エンジニアのキャリアパスや成長環境についても具体的に説明すると、将来のイメージがしやすくなります。
例えば、「入社1年目でこのようなプロジェクトに関わることができた」「社内の勉強会が充実している」「技術的な挑戦がしやすい環境」など、実際の経験を伝えることで、求職者にとって魅力的な情報となります。
これらのインタビュー記事は、採用ページや企業ブログ、SNSで発信することで、より多くの求職者の目に留まるようにすると効果的です。
動画コンテンツとして配信するのも良い方法でしょう。
ピッチ資料を作成する
企業の魅力を求職者に伝えるためには、ピッチ資料(会社紹介資料)の作成が欠かせません。
エンジニアは、多くの企業からスカウトを受けるため、興味を持ってもらうためには短時間で企業の魅力を伝える工夫が必要です。
ピッチ資料には、会社のビジョンや事業内容、プロダクト、技術スタック、エンジニア組織の特徴などを明確に記載します。
特にエンジニア向けの資料では、「使用している技術」「チームの開発スタイル」「コードレビューの文化」「働き方の自由度」など、エンジニアが重視するポイントを盛り込むことが大切です。
また、実際に働いているエンジニアの声や、過去のプロジェクト事例を掲載することで、よりリアルなイメージを持ってもらうことができます。
さらに、福利厚生やリモートワークの有無、副業可否などの情報も記載すると、求職者の判断材料として役立ちます。
ピッチ資料は、スカウトメールに添付したり、面談時に説明資料として使用したりすると効果的です。
視覚的に分かりやすく、シンプルな構成にすることで、求職者にとって負担の少ない資料に仕上げることがポイントです。
選考プロセスを透明化する
求職者にとって、選考プロセスが不透明な企業は不安要素が多く、応募をためらう原因になります。
「何回面接があるのか」「どのような内容が評価されるのか」「選考期間はどれくらいかかるのか」といった情報が不明確だと、他社と比較して敬遠されることも少なくありません。
そのため、企業側は選考プロセスを明確にし、事前に伝えることが重要です。
例えば、採用ページやスカウトメールに「書類選考 → 一次面接(技術面談) → 最終面接(カルチャーフィット確認)」のように具体的なフローを記載することで、求職者が準備しやすくなります。
また、それぞれのステップで何を評価するのかを明示すると、より安心感を与えることができます。
面接官の役職や、技術テストの有無、所要時間を明確にすることも有効です。
例えば、「一次面接ではCTOが技術面談を担当し、実際のプロジェクトに関する質問を行います」「二次面接は1時間で、カルチャーフィットを重視した対話を行います」と具体的に説明すると、求職者が心の準備をしやすくなります。
さらに、選考中のフィードバックを適宜伝えることで、求職者とのコミュニケーションを円滑にし、内定後の辞退リスクを減らすことができます。
選考をできるだけ迅速に進める
エンジニアの転職市場は競争が激しく、優秀な人材ほど複数の企業からオファーを受けています。
そのため、選考スピードが遅いと、他社に先を越されてしまう可能性が高くなります。
例えば、書類選考に1週間以上かかる企業と、2日以内に結果を出す企業があった場合、求職者は後者に対して「スムーズな対応をしてくれる」と好印象を持ちやすくなります。
面接後の合否連絡が遅れると、求職者の関心が薄れ、結果的に辞退されることも少なくありません。
選考を迅速に進めるためには、面接官のスケジュールを事前に調整し、迅速にフィードバックを送る体制を整えることが重要です。
特に、技術テストやコード課題の提出を求める場合は、できるだけ短期間で結果を通知することで、求職者のストレスを軽減できます。
また、人事だけでなく開発チームとの連携をすることも重要です。
スピード感のある対応は、企業の印象を向上させるだけでなく、求職者が他社との比較をする前に意思決定をしやすくするという効果もあります。
スカウトメールの質を向上させる
エンジニア採用では、求人を出して待つだけでは優秀な人材を確保するのが難しく、ダイレクトリクルーティング(スカウトメール)を活用することが重要です。
しかし、単に一斉送信のスカウトメールを送るだけでは、多くのエンジニアに無視されてしまいます。
スカウトメールの開封率や返信率を向上させるには、求職者に「この企業は自分に興味を持ってくれている」と感じてもらうことが大切です。
例えば、テンプレートではなく、以下のように相手に合わせたカスタマイズを行うことで、返信率が上がります。
- 「あなたのGitHubのプロジェクトを拝見しました」
- 「ポートフォリオの〇〇という技術に興味を持ちました」
- 「以前〇〇社でのご経験があるとのことで、当社の開発環境とも相性が良いのではと考えました」
長文のスカウトメールは読まれにくいため、「当社では最新の〇〇技術を活用した開発に携われます」といった簡潔なメッセージを入れて会社の魅力を簡潔に伝えると、より印象に残りやすくなります。
また、以下のように、興味を持ってもらうフックを作ることも効果的です。
- いきなり「選考を受けませんか?」ではなく、「カジュアル面談でお話しませんか?」といった柔軟な提案をする。
- 「当社のエンジニアブログをぜひご覧ください!」と、関連情報へのリンクを入れる。
スカウトメールは「企業が求職者を評価する場」ではなく、「求職者に企業の魅力を伝える場」であることを意識しましょう。
応募のハードルを下げる
優秀なエンジニアほど、転職活動に慎重になる傾向があります。
特に、現在の職場で一定の満足度がある場合、「選考に進むかどうか迷う」と感じることが多くなります。
そこで、企業側が応募のハードルを下げる工夫をすることが重要です。
例えば、「いきなり書類選考→面接」ではなく、「まずはオンラインで気軽に話しましょう」とカジュアル面談を提案することで、求職者の心理的ハードルを下げると良いでしょう。
また、以下のようにスキルチェックの負担を軽減することも効果的です。
例えば、「技術課題に3時間かかる」など負担が大きいと、優秀なエンジニアほど敬遠するため、「過去の成果物(GitHubやポートフォリオ)を提出可」とすることで、求職者の負担が減ります。
転職を希望するエンジニアは、仕事をしながら転職先を探しているケースがほとんどなので、以下のように柔軟な選考フローを設けることも重要です。
- 「仕事が忙しくて面接時間が取れない」という人向けに、夜間や休日の面談も可能にする。
- 「1次面接を省略して最終面接に進める」など、スキルが明確な人に対して選考をスピーディーにする。
これらの施策を取り入れることで、「とりあえず話を聞いてみようかな」と思ってもらいやすくなり、応募数の増加につながります。
内定者フォロー面談により不安を取り除く
無事に内定を出せても、入社前に辞退されてしまうケースは少なくありません。
特にエンジニアの場合、複数の企業からオファーを受けることが多いため、他社との比較の中で辞退を決めることがあります。
そこで、内定者フォロー面談を実施し、求職者の不安を解消することが重要です。
具体的には、以下のように内定後の面談やヒアリング、自社の社員との交流機会を設けることで、求職者の不安を取り除くと良いでしょう。
- CTOや現場エンジニアと1対1の面談を行い、「実際の開発チームの雰囲気」や「入社後のプロジェクト」について具体的に話す。
- 「今後どのように成長していけるのか?」といったキャリアパスについて相談する。
- 「技術的なキャッチアップに不安がある」といった悩みには、「事前に社内勉強会の資料を共有する」などのサポートを行う。
- 「入社前のランチ会」や「SlackやDiscordへの招待」など、チームメンバーと気軽に話せる機会を設けることで、入社後のミスマッチを防ぐ。
内定後のフォローをしっかり行うことで、辞退を防ぎ、スムーズな入社へとつなげることができます。
スムーズに業務に取り掛かれるように支援する
エンジニアが入社後にすぐに活躍できるよう、オンボーディング(入社後の支援)を強化することが大切です。
適切なサポートがないと、エンジニアが「この会社で本当にやっていけるのか?」と不安になり、早期離職のリスクが高まります。
例えば、以下のような事前準備をしておくと良いでしょう。
- PCや開発ツールのセットアップを事前に済ませておく。
- アカウント発行(GitHub、Slack、社内システムなど)を入社前に完了しておく。
- 社内の技術ドキュメントや、過去のプロジェクト資料を提供する。
エンジニアがスムーズに業務に馴染めるようサポートすることで、定着率が向上し、長期的な活躍につながります。
エンジニアの中途採用で重要な「認知」を獲得するには?
ここまで解説してきたとおり、エンジニアが抱えている不安を解消するような施策を行うことにより、優秀なエンジニアからの募集・採用できる可能性は高まります。
しかし、いくら自社がエンジニアにとって最適な環境を整えていても、それをエンジニアに認知してもらえなければ、全く意味がありません。
しかし、多くのエンジニアの認知を獲得するには、SNSの活用やイベント・勉強への参加、外部メディアでの露出など、各施策を活用しながら長期目線での施策が必要となるため、社内のリソースだけでは限界を感じて悩んでいる企業も多いのではないでしょうか?
そこでおすすめなのが、PERSOLグループが提供する採用ブランディング支援サービス「TECH PLAY Branding」 です。
27万人以上が利用するエンジニア向け学習プラットフォーム「TECH PLAY」を通じてイベントや勉強会を実施することにより、効率的にエンジニアとの接点を持てます。
さらに採用サイトやオウンドメディアの制作・運用など、一貫した採用マーケティング・ブランディング支援により、効果的かつ効率的にエンジニアからの認知を獲得できます。
今なら、TECH PLAY Brandingサービス紹介ページから、エンジニア採用のノウハウが掲載された資料を無料でダウンロードできるので、興味のある方はぜひ一度ご覧ください。
まとめ
エンジニアの中途採用を成功させるには、単に求人を出すだけでなく、エンジニアの視点に立った採用戦略が必要です。
給与やスキルアップ、働きやすさなど、エンジニアが重視するポイントを明確に伝え、採用プロセスの最適化を図ることで、優秀な人材の確保につながります。
企業の魅力をしっかり伝えつつ、エンジニアの不安を解消する施策を実践し、中途採用の成功率を高めていきましょう!

この記事を書いた人
TECH PLAY BUSINESS
パーソルイノベーション株式会社が運営するTECH PLAY。約23万人※のテクノロジー人材を会員にもつITイベント情報サービスの運営、テクノロジー関連イベントの企画立案、法人向けDX人材・エンジニア育成支援サービスです。テクノロジー人材のエンパワーメントと企業のDX化の成功をサポートします。※2023年5月時点
よく読まれている記事
\「3分でわかるTECH PLAY」資料ダウンロード/
事例を交えて独自のソリューションをご紹介します。