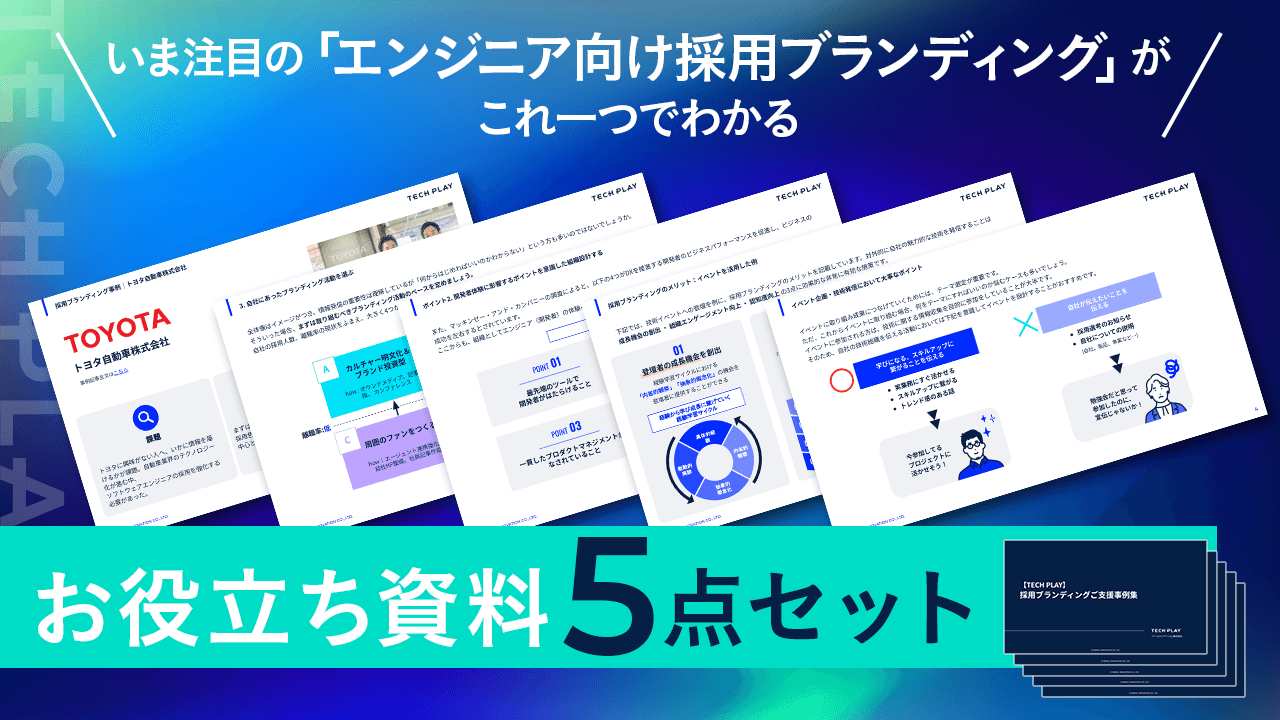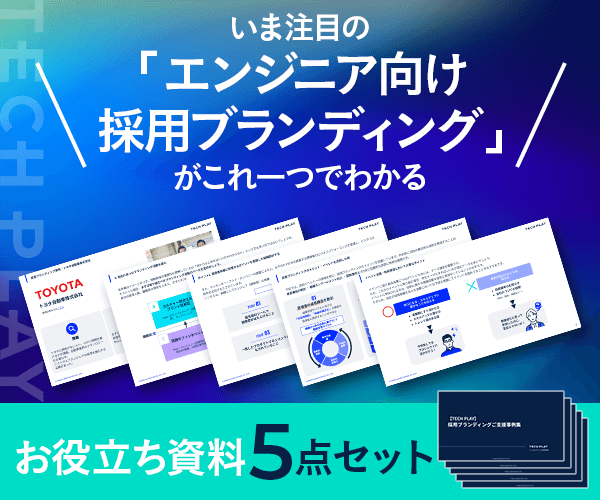エンジニア採用のコツ12選【すぐ実践できる具体的な施策を解説】
エンジニア採用は、企業の成長や競争力を左右する重要なプロセスです。
しかし、優秀なエンジニアを確保することは容易ではなく、多くの企業が採用活動に苦戦しています。
本記事では、エンジニア採用の成功に向けた具体的なコツ12選を、認知フェーズ・応募フェーズ・内定〜入社フェーズの3つに分けて解説します。
また、持続的に優秀なエンジニアを採用し続けるために、採用ブランティングを成功させるコツや、エンジニア採用を成功させるための組織づくりのコツも解説するので、エンジニア採用に課題を抱えている方はぜひ最後までご覧ください。
目次
エンジニア採用のコツ(①認知フェーズ)
エンジニア採用を成功させるには、まず企業の存在や魅力をターゲットとなるエンジニアに知ってもらうことが重要です。
この認知フェーズでは、単に求人広告を出すだけでなく、企業の技術力や社内の取り組みを発信し、エンジニアが興味を持つきっかけを増やしましょう。
エンジニアの採用市場は競争が激しく、優秀な人材は企業から積極的にアプローチされるのが一般的のため、「エンジニアがこの会社で働いてみたい」と思うようなブランディング施策が理想的です。
本章では、認知フェーズにおけるエンジニア採用の具体的なコツを4つご紹介します。
採用チャネルを増やす
エンジニア採用を成功させるためには、複数の採用チャネルを活用することが重要です。
一般的な求人サイト、媒体、人材紹介会社や転職エージェントだけでなく、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用(社員紹介)、SNS、エンジニアコミュニティなど、多様な方法を組み合わせることで、より多くの候補者にアプローチできます。
ダイレクトリクルーティングは、優秀なエンジニアにピンポイントでアプローチできるため、効率的な採用手法のひとつです。
LaprasやForkwellなどのエンジニア特化型のスカウトサービスを活用すると、より精度の高いターゲティングが可能になります。
また、リファラル採用(紹介による採用)を強化することで、社員の紹介による信頼度の高い候補者を集めることもできます。
自社だけでの採用活動が難しい場合は、採用代行も検討しましょう。
採用のプロに支援いただくことで成果につながるケースも多いです。
加えて、エンジニアが集まるプラットフォーム(GitHub、Qiita、Zenn、Xなど)で情報発信を行い、企業の存在を知ってもらうことも有効です。
採用チャネルを増やし、それぞれの特性を活かしてアプローチすることで、より多くのエンジニアに自社の魅力を伝えられるでしょう。
自社サイトの求人情報を充実させる
転職サイトやスカウトサービスを通じて企業に興味を持ったエンジニアは、高い確率で企業の公式サイトを訪れ、詳しい情報をチェックします。
そのため、自社の採用ページをエンジニア目線で充実させる必要があります。
エンジニアにとって魅力的な採用ページを作るためには、以下のような情報を詳しく記載することがポイントです。
- 開発環境・使用技術の詳細(プログラミング言語、フレームワーク、インフラ、CI/CDツールなど)
- エンジニアの働き方(リモートワーク可否、フレックスタイム、裁量権など)
- 実際に働くエンジニアのインタビューや座談会記事(チームの雰囲気が伝わるようにする)
- 社内の技術的な取り組みや課題(どのような技術スタックで、どんな課題に取り組んでいるのか)
- 福利厚生(資格取得・スキルアップに対する支援や休暇取得制度など)
また、採用ページのデザインや文章も、ターゲットに刺さる形にすることが大切です。
過度にビジネスライクな表現ではなく、エンジニアが共感しやすい言葉を使い、リアルな職場の雰囲気を伝えることを意識しましょう。
合わせて、エンジニア向けの採用ピッチ資料を作成し、webサイトヘ掲載することも効果的です。
サイトだけでは伝えきれない自社の特徴や強みを伝えることができるメリットがあります。
オウンドメディア・SNSなどで技術力を発信する
企業の技術力や開発環境を重要視するエンジニアも多いです。
自社の技術力を発信することで、優秀なエンジニアに「この会社なら面白い仕事ができそう」と思ってもらうことができます。
技術ブログ(オウンドメディア)を活用し、社内で取り組んでいる技術や課題解決のプロセスを公開すると、エンジニアの関心を引きやすくなります。
具体的には、以下のような内容を発信すると効果的です。
- 新しい技術を導入した事例(例:「Goを導入してパフォーマンスが向上した話」)
- 技術選定の理由と背景(例:「なぜこのフレームワークを採用したのか」)
- 開発チームの文化やワークフロー(例:「リモート開発におけるコミュニケーションの工夫」)
また、SNS(X、LinkedIn、YouTubeなど)での発信も効果的です。
エンジニアはSNSを通じて情報収集を行うことが多いため、企業のエンジニアが定期的に技術情報を発信することで認知度を高められます。
さらに、エンジニア向けのカンファレンスや勉強会で登壇することで、企業の技術力をアピールすることで優秀なエンジニアに認知されやすくなります。
「技術に強い企業」という印象を持たれることで、採用活動がスムーズになるでしょう。
エンジニア向けイベントや勉強会に参加する
エンジニアを採用するには、単に求人を出すだけでなく、エンジニアが集まる場所に積極的に参加することが重要です。
勉強会やハッカソン、技術カンファレンスなどに参加・協賛することで、優秀なエンジニアとの接点を作ることができます。
具体的には、以下のようなイベントに関与するのが効果的です。
- エンジニア向け勉強会やMeetupに登壇・スポンサーとして参加
- 社内で技術イベントを開催し、外部のエンジニアと交流する
- OSS活動を支援し、技術コミュニティとのつながりを強化する
特に、「社内で技術勉強会を開催し、外部のエンジニアも招く」という取り組みは、採用ブランディングに非常に有効です。
例えば、「社内で使っている技術についての発表会」や「特定の技術をテーマにしたハンズオンイベント」を開くことで、エンジニア同士の交流が生まれ、自然な形で採用につながります。
また、ハッカソンのスポンサーになることで、エンジニアとの接点を増やすのも効果的です。
実際に企業のエンジニアが参加し、開発を一緒に行うことで、企業文化や技術レベルをアピールすることができます。
エンジニア採用のコツ(②募集〜選考フェーズ)
エンジニア採用において、認知フェーズで興味を持ってもらえたとしても、実際に応募してもらい、選考を進めていく段階で離脱されてしまっては意味がありません。
エンジニアの採用市場は売り手市場であり、求職者は複数の企業からのオファーを比較して選ぶ立場にあります。
そのため、スムーズな選考フローを設計し、エンジニアが安心して応募・選考を進められる環境を整えることが重要です。
エンジニアは、技術スキルや働き方へのこだわりが強く、求人情報が不明瞭だったり、選考プロセスが煩雑だったりすると、途中で辞退される可能性が高まります。
逆に、選考の透明性を確保し、応募から内定までのプロセスをスムーズに進めることで、優秀なエンジニアを獲得しやすくなります。
ここでは、エンジニアが安心して応募・選考を進められるようにするための具体的なコツを5つ解説します。
求人情報を明確にする
エンジニア採用において、求人情報は想像よりも細かく記載する必要があります。
具体的な業務内容や技術スタックが曖昧だと、求職者は「自分に合っているのかわからない」と感じてしまい、応募をためらう原因になります。
具体的には、以下のような項目を明確に記載することが重要です。
- 技術スタック(例:バックエンドはGo、フロントエンドはReactなど)
- 開発するサービスの種類(例:「SaaS型のマーケティングツール」「ECサイトのプラットフォーム開発」など)
- 主な開発業務例:「決済システムの設計」「レコメンド機能の開発」「モバイルアプリのUI改善」など
- 開発環境(例:「AWS環境」「Dockerを利用」「アジャイル開発」など)
- チーム体制や働き方(例:「エンジニア5名+デザイナー2名で開発」「リモートワーク可」など)
また、求めるスキルレベルの記載も工夫が必要です。
「開発経験1年以上」などの年数による制限を設けるのではなく、求める技術力や経験の具体例を示すと、実力のあるエンジニアが応募しやすくなります。
例えば、
- 「Python(Django)を用いたAPI開発経験があり、設計から実装まで対応できる方」
- 「Reactを用いたフロントエンド開発で、パフォーマンス改善の経験がある方」
- 「DockerやAWSを用いた環境構築・運用の知識がある方」
このように具体的な業務内容やスキル要件を明確にすることで、求職者は自分がフィットするかどうか判断しやすくなり、ミスマッチを防ぐことができます。
さらに、給与や福利厚生、働き方(フルリモート可・出社必須など)も明示することで、応募率の向上につながります。
選考プロセスを透明化する
エンジニア採用において、選考フローが不透明だと求職者が不安を感じ、応募を躊躇してしまいます。
エンジニアは複数の企業の選考を同時に受けていることが多いため、「この会社の選考がどのくらいの期間かかるのか」「どんな評価基準なのか」が明確でないと、他社の選考に進んでしまう可能性があります。
選考の透明化を図るために、以下のような情報を事前に求職者に伝えておくことが重要です。
- 選考の流れを明示する(例:「書類選考 → 一次面接(技術面談)→ 二次面接(カルチャーフィット)→ 最終面接」)
- 各選考ステップの所要期間を伝える(例:「書類選考は3営業日以内に結果を通知」「最終面接後5日以内に合否を連絡」)
- 選考時の評価基準を共有する(例:「技術面談では、コーディングスキルと設計力を確認」「カルチャーフィット面接では、チームワークとコミュニケーション力を重視」)
- 面接官の役職や人数を明示する(例:「一次面接はエンジニアリーダー1名」「二次面接は開発部長+HR担当の2名」「最終面接はCTOとCEOの2名」)
これらの情報を事前に提示することで、求職者は安心して選考に臨むことができ、辞退率を下げることができます。
選考をできるだけ迅速に進める
エンジニアの転職市場では、選考が長引くと他社に先を越されてしまうことがよくあります。
優秀な人材ほど、短期間で複数の企業からオファーを受けるため、スピード感のある対応が重要です。
具体的には、以下のような施策を取り入れるとよいでしょう。
- 書類選考は3営業日以内に結果を出す
- 面接後、できる限り早く合否を通知する(遅くとも5日以内が理想)
- 面接のスケジュール調整を柔軟に行う(夜間や土日対応を検討)
- 一次面接と二次面接をまとめて実施する(候補者の負担を減らす)
スムーズな選考プロセスを提供することで、求職者のモチベーションを維持し、内定辞退を防ぐことができます。
スカウトメールの質を向上させる
ダイレクトリクルーティングを活用する際、スカウトメールの質が低いと無視される確率が高くなります。
エンジニアは日々多くのスカウトを受け取っており、定型文のようなメールでは埋もれてしまいます。
返信率を高めるためには、以下のポイントを意識しましょう。
- 候補者の実績に触れる(「GitHubでの〇〇のプロジェクトを拝見し、技術力に感銘を受けました」)
- なぜ興味を持ったのか明確に伝える(「弊社の技術スタックが〇〇で、あなたの経験とマッチすると考えました」)
- 興味を持ちやすい内容を含める(「まずはカジュアル面談でお話ししませんか?」)
パーソナライズされたスカウトメールを送ることで、返信率が向上し、採用の成功率を高めることができます。
応募のハードルを下げる
エンジニア採用では、できるだけ多くの候補者に応募してもらうことが重要です。
しかし、応募の手間がかかると、興味があっても行動に移さない求職者が増えてしまうため、応募のハードルを下げる工夫が必要です。
応募書類を簡単なフォームにするなど、負担を減らす工夫をすると応募が増える可能性があります。
また、カジュアル面談を導入するのも効果的です。
「話を聞くだけでもOK」というスタンスにすることで、転職を迷っているエンジニアにも興味を持ってもらいやすくなります。
面談では、会社の技術環境や開発体制について丁寧に説明し、「ここで働きたい」と思ってもらえるような情報を提供することが重要です。
最後に、応募フォームを簡略化することもポイントです。
入力項目が多すぎると、途中で離脱される可能性が高まります。
「氏名・メールアドレス・ポートフォリオのURL」程度の簡単な入力で応募できるようにすると、応募数の増加につながります。
このように、応募のハードルを下げることで、より多くのエンジニアに興味を持ってもらい、選考に進んでもらえる可能性が高まります。
エンジニア採用のコツ(③内定〜入社フェーズ)
エンジニア採用は、内定を出して終わりではありません。
内定者が安心して入社できるようにフォローし、スムーズに業務へ移行できる環境を整えることが重要です。
特にエンジニアは転職市場での需要が高いため、内定辞退を防ぐための対策が必要になります。
また、入社後のオンボーディングが適切に行われないと、早期離職のリスクも高まるため、しっかりとした準備が求められます。
本フェーズでは、内定者フォローを通じて不安を解消し、入社意欲を高めることがポイントです。
加えて、入社後にスムーズに業務を開始できるような支援体制を整えることも欠かせません。
本章では、内定〜入社フェーズにおいて、求職者に内定を辞退せずに入社してもらうコツを2つ解説します。
内定者フォロー面談により不安を取り除く
内定者フォローは、内定者が不安なく入社できるようサポートする重要なプロセスです。
エンジニアは転職先を慎重に選ぶ傾向があり、内定後も「本当にこの会社で大丈夫か?」と不安を感じることがあります。
そのため、定期的なフォロー面談を行い、安心して入社を迎えられるよう支援することが大切です。
まず、内定通知後にフォロー面談を実施することで、不安や疑問を直接解消できます。
面談では、業務内容や開発環境を再確認し、求職者の希望とのズレをなくすことが重要です。
また、エンジニア同士の交流を深めるために、現場のエンジニアとのカジュアルな面談を設定するのも効果的です。
実際に働くメンバーと話すことで、職場の雰囲気や働き方について具体的なイメージを持ってもらえます。
さらに、オファー面談でキャリアパスや具体的なスキルアップ支援内容を伝えることも有効です。
エンジニアはスキルアップを重視する人が多いため、入社後のキャリアパスや技術的な挑戦ができる環境について具体的に説明することで、入社意欲を高められます。
このように、内定者フォローを充実させることで、安心感を与え、内定辞退を防ぐことができます。
スムーズに業務に取りかかれるよう支援する
エンジニアが入社後にスムーズに業務を開始できるかどうかは、企業側の準備次第です。
環境が整っていないと、エンジニアはストレスを感じ、早期離職のリスクが高まります。
そのため、事前準備を徹底し、円滑にオンボーディングを進めることが重要です。
まず、入社前に必要な環境を整備することが基本です。
PCのセットアップや開発環境の準備、アカウント発行などを事前に完了しておくことで、入社初日からスムーズに業務を開始できます。
また、開発フローやプロジェクトの進め方をまとめたドキュメントを用意することで、新しいメンバーが業務に慣れるまでの時間を短縮できます。
次に、オンボーディングプログラムを用意することも効果的です。
例えば、最初の1〜2週間で学ぶべき内容をリスト化し、エンジニアが自主的にキャッチアップできる仕組みを整えると、負担を軽減できます。
併せて、メンター制度を導入することで、新入社員が気軽に質問できる環境を作るのも良いでしょう。
さらに、早期にチームへ参加できる仕組みを整えることも重要です。
最初のタスクを小さめに設定し、簡単なバグ修正やドキュメントの改善などを担当してもらうことで、無理なく業務に慣れてもらえます。
また、定期的なフォローアップ面談を実施し、不安や課題を早めに解決できるようサポートすることも必要です。
このように、入社前後の準備を整え、オンボーディングをスムーズに進めることで、新しいエンジニアが安心して業務に取り組める環境を作れます。
エンジニアの採用ブランディングを成功させるコツは?
エンジニア採用において、優秀な人材を惹きつけるためには「採用ブランディング」が欠かせません。
エンジニアは、企業の知名度だけでなく、技術力・働きやすさ・成長環境といった要素を重視する傾向があります。
そのため、「この会社なら成長できそう」「働きやすそう」と思ってもらえるようなブランディング戦略が重要になります。
しかし、効果的な採用ブランディングを実践するには、適切な発信手法やエンジニアとの接点を持つ場が不可欠です。
そこでおすすめなのが、採用ブランディング支援サービス「TECH PLAY Branding」 です。
TECH PLAY Brandingは、エンジニア向けのイベントやセミナーでの自社の技術情報の発信を通じて、企業の技術力やカルチャーをアピールし、採用につなげるためのサービスです。
28万人以上のテクノロジー人材が登録するエンジニア向け学習プラットフォームを活用し、効果的にエンジニアへのアプローチができます。
特に、採用サイトや技術ブログ、SNS、イベントなどを活用し、企業の強みや開発環境、カルチャーを継続的に発信することは、エンジニアからの共感を得る上で非常に有効です。
TECH PLAY Brandingを活用すれば、企業とエンジニアが直接つながる場を作ることができ、より深い関係を築くことができます。
このように採用ブランディングを強化することで、「この企業で働きたい」と思うエンジニアが増え、結果として応募数の増加や選考辞退率の低下につながります。
エンジニア採用を成功させるための組織づくりのコツは?
エンジニア採用の成功は、単に優秀な人材を確保するだけではありません。
採用したエンジニアが長期的に活躍できる環境を整え、定着率を高めることが重要です。
特に、エンジニアが働きやすい組織文化や評価制度の整備、現場のエンジニアを巻き込んだ採用活動は、採用の質を向上させるための重要な要素になります。
ここでは、エンジニア採用を成功に導くための組織づくりのコツを解説します。
エンジニアが定着しやすい環境を作る
エンジニアが長く働き続けられる環境を作るためには、快適な労働環境や成長の機会を提供することが不可欠です。
エンジニアは孤独感を感じやすい職種のため、部署やグループを超えたエンジニア間の交流
が重要です。
例えば、複数の事業部やグループ会社を持つ企業では、エンジニア同士のつながりが希薄になりがちです。
定期的な勉強会やカジュアルな交流イベントを開催することで、部門間のコミュニケーションを活性化し、相互理解を深めることができます。
また、エンジニアの成長と成果を正当に評価するために、既存の評価制度を見直し、明確な基準を設定することも重要です。
評価制度が明確だと、エンジニアは自身のキャリアパスを明確に描くことができ、モチベーションの向上につながります。
さらに、社内での技術勉強会や外部のカンファレンス参加を奨励し、スキルアップの機会を提供することも重要です。
これにより、エンジニアは自分の成長を実感でき、職場に対する帰属意識が高まるでしょう。
現場のエンジニアにも採用活動に関与してもらう
採用活動を人事部門だけで進めるのではなく、現場のエンジニアにも関与してもらうことが重要です。
技術選考や面接に現場のエンジニアを参加させることで、応募者の技術力を正しく評価し、実際の業務に適した人材を選べます。
また、エンジニアが自らの言葉で社内の雰囲気や技術的な魅力を伝えることで、求職者にとっての企業の魅力が伝わりやすくなります。
さらに、現場のエンジニアが参加する技術広報活動や勉強会を通じて、エンジニア同士のつながりを深めることで、リファラル採用の促進も期待できます。
このように、エンジニアが採用活動に参加することで、より良いマッチングを実現しやすくなります。
エンジニアの評価制度を最適化する
エンジニアのモチベーションを維持するためには、公平で納得感のある評価制度を整える必要があります。
成果を正当に評価するための基準を設定し、開発プロジェクトでの貢献度やコード品質、技術的な提案などを評価の対象とします。
また、成長を促すために、年に数回の評価だけでなく、定期的にフィードバックを行う仕組みを作ることが重要です。
1on1ミーティングを実施し、エンジニアのキャリア目標を確認することで、エンジニアが思い描くキャリアパスの実現をサポートします。
さらに、技術スペシャリスト向けとマネジメント向けの異なる評価基準を設け、個々のキャリアパスに応じた評価を行うことで、エンジニアのやる気を引き出すことができます。
このように、エンジニアが成長を実感し、会社に対する貢献度を感じられるような評価制度を構築することで、定着率を高めることができるでしょう。
エンジニア採用におけるよくある失敗
エンジニア採用に苦戦する理由は、IT人材の不足などの外部環境の影響だけではありません。
実は、企業側の内部的な要因が採用のハードルを上げてしまっていることも多いのです。
どんなに採用活動に力を入れても、正しいやり方で進めていかなければ、思ったような効果は得られません。
ここからは、企業が無意識のうちにやってしまいがちな失敗例をご紹介します。
企業がエンジニア採用に苦戦する詳しい原因については、以下の記事で詳しく解説していますので、興味のある方はぜひこちらもご覧ください。
参考記事:エンジニア採用は難しい?苦戦する理由とやるべき17の対策【成功事例あり】
エンジニアへの認知度が低い
どれだけ魅力的な環境や待遇を用意していても、エンジニアに認知されていなければ応募にはつながりません。
特に、スタートアップや知名度の低い企業は、そもそもターゲット層に情報が届いていないケースが多いです。
「求人を出せば見てもらえる」という考えでは、なかなか応募者が集まらないのが現実です。
採用ターゲットが明確でない
「即戦力がほしい」「ポテンシャル採用も考えたい」と、求める人物像が曖昧なまま採用活動を進めていませんか?
ターゲットが明確でないと、求人の打ち出し方もぼやけてしまい、エンジニア側も「自分に合ったポジションなのか」が分からず、応募をためらってしまいます。
また、面接時の評価基準もブレやすく、結果として「なんとなく良さそうだから採用」「求める人材と少し違うが妥協して採用」といった判断が増え、ミスマッチが発生しやすくなります。
採用担当者のエンジニアリングへの知識の欠如
採用担当者がエンジニアリングに関する知識を持っていないと、求人票を作成する際に内容が的外れになったり、面接で適切な質問ができなかったりすることがあります。
エンジニア側からすると、「技術の話が通じない」「採用担当者が求めているスキルが分からない」と感じ、興味を失ってしまうことも。
採用担当者のエンジニアリングへの知識が欠如していることは、採用活動の過程でミスマッチが生じやすくなる要因のひとつです。
開示している情報が少ない
エンジニアにとって、使用する技術や開発フロー、具体的な職場環境や福利厚生は非常に重要なポイントです。
しかし、求人票や採用ページに、そういったエンジニアが欲しい情報がほとんど載っていない企業も多く、結果として応募を逃してしまいます。
「どんな技術を使っているのか」「どんなチームで働くのか」「リモートワークは可能なのか」といった情報が不足していると、エンジニアは判断材料を得られず、別の企業を選んでしまうこともあります。
エンジニアにとって魅力的な求人票になっていない
エンジニア向けの求人票は、単なる業務内容や募集要項の羅列ではなく、「この会社で働く魅力」を伝えることが重要です。
しかし、よくある求人票は「スキル要件」「給与」「福利厚生」の情報しかなく、エンジニアに響かないケースが少なくありません。
「この会社で働くと、どんな成長ができるのか」「どんな課題にチャレンジできるのか」など、エンジニアがワクワクするような要素がなければ、他の求人と比較されて埋もれてしまいます。
企業とエンジニア間で条件面にギャップがある
企業が提示する条件と、エンジニアが求める条件にギャップがあると、選考が進んでも内定辞退につながりやすくなります。
例えば、エンジニアは「リモートワークやフレックスタイム」を希望しているのに、企業は「出社必須」としている場合、ミスマッチが起こります。
企業側が提示する給与や待遇、業務内容、働き方の条件と、エンジニアが求めるものに差があると、応募が集まりにくくなり、せっかく内定を出しても辞退されるケースが増えてしまいます。
採用選考フローが明確でない
「面接は何回あるのか」「技術試験はあるのか」「どれくらいの期間で合否が出るのか」といった選考フローが曖昧だと、応募者の不安が募ります。
特に、他社と並行して選考を進めているエンジニアにとって、選考フローの不透明さは大きなストレスになります。
「この会社のプロセスがよく分からないから、選考を辞退しよう」と思われてしまうこともあります。
採用選考の期間が長すぎる
選考に時間をかけすぎると、エンジニアは待っている間に他社のオファーを受け、そちらを選んでしまうことがあります。
特に、優秀なエンジニアほど複数の企業から声がかかっているため、選考期間が長い企業はどうしても不利になります。
「一次面接から最終面接まで1ヶ月以上かかる」といったケースでは、競争に負けてしまう可能性が高くなります。
応募者のスキル評価の基準が曖昧
「このスキルがある人を採用したい」と言いながら、実際の選考で評価基準が統一されていないと、せっかくの応募者を取りこぼしてしまいます。
また、採用基準が曖昧だと、「この人は何となく合わなさそう」という主観的な判断で不採用になるケースも出てきます。
結果として、優秀なエンジニアを逃してしまい、採用が難しくなってしまいます。
エンジニア採用の参考になる成功事例9選
採用市場が厳しい中でも、効果的な施策を実施し、エンジニア採用を成功させている企業も存在します。
本章では、エンジニア採用に成功している企業の具体的な事例を9例ご紹介します。
ブランディングの強化、採用フローの工夫、魅力的なオファーの提示など、それぞれの企業がどのような工夫をしているのかを詳しく解説します。
自社の採用活動に活かせるヒントを見つけてください。
採用広報に注力したエンジニアの採用事例5選
採用広報も採用活動に効果的です。
採用広報に注力した企業の事例を9つ紹介します。
事例1.トヨタ自動車株式会社
トヨタ自動車株式会社は、ソフトウェアファーストなモノづくりのため、優秀なエンジニアを求めていました。
しかし、自動車産業がエンジニアを必要としている状況があまり認知されていませんでした。
同社は、TECH PLAYでのイベントを通じて技術や課題の認知に努めています。
1回のイベントにあたり、800人程度を集客でき、採用活動を強化できました。
また、同社は、採用サイトにTECH PLAYイベントアーカイブを掲載中です。
アーカイブでは、TECH PLAYのウェビナー動画や、具体的な開発事例を視聴できます。
※参考:トヨタ自動車がソフトウェアエンジニア採用を強化 採用ブランディング成功の秘訣とは
※参考:トヨタ自動車㈱ のイベント・技術情報|TECH PLAY
事例2. 株式会社NTTデータ
1988年の設立以来、日本のシステムインテグレーション業界をけん引し、今なお国内トップSIerとして業界をリードする株式会社NTTデータ。
「2023年卒の就活生が選ぶIT業界新卒就職人気企業ランキング」(楽天「みん就」発表)では1位を獲得するほどの人気企業ですが、一方で経験者採用には「事業の認知度不足」という課題も抱えていました。
社会的価値が高く魅力的な業務の認知度を上げるべく、NTTデータの中でも製造業・流通業・サービス業等顧客を対象とする法人分野では、2021年より採用ブランディングを実施。
TECH PLAYも導入していただき、今まさに効果を実感しているとのことです。
※参考:NTTデータの“真の魅力”を継続的に届ける 優秀な人材確保につながった採用ブランディングの手法とは
事例3. アバナード株式会社
アクセンチュアとマイクロソフトの戦略的合弁企業として2000年に米国でスタートしたアバナード株式会社。
マイクロソフトのテクノロジーとアクセンチュアのビジネスの知見を生かし、コンサルティングからシステムの設計・開発・導入・保守までワンストップで提供しています。
IT業界でも一目置かれるグローバル企業です。
技術発信の場としてTECH PLAYもご利用いただいていますが、そのイベントは、「IoTの力でビールを醸造してみた」「AI判定型ビリビリクイズマシンを作ってみた」など、個性的なものが多いのも特徴。
現在採用も急拡大する中、斬新な技術発信に力を入れ、採用につなげています。
※参考:「テックビール」「ビリビリクイズマシン」!? アバナードが斬新な技術発信に力を入れる理由
事例4. 株式会社AGEST
ソフトウェアのQA専門の会社として、ソフトウェアテスト、システムインテグレーション、セキュリティ分野における課題解決をワンストップで提供する株式会社AGEST(以下AGEST)。
技術広報の一環としてTECH PLAYも導入いただいております。
AGESTがTECH PLAYを導入いただいた大きな理由には、ソフトウェア開発におけるQAの重要性を広めたいという想いがありました。
ソフトウェアにおけるQAの重要度は高まっているにも関わらず、日本国内全体でQAに対する認知度・関心度が低い。
採用を見据えたうえで、まずはこの価値観そのものを変えていく必要があるという課題を抱えていた同社。
テックカンパニーとしてQAの認知度向上を最大の目的としつつ、「QAエンジニア」という職業をキャリアの選択肢をブランディングする効果を狙ってTECH PLAYでウェビナーを実施。
これまで開催した全ウェビナーで定員を当初の予定より増員するほど集客は好調。計4回のイベントで980名増員という結果に。集まる学生も意識の高い方が増えているそうです。
※参考:「QAの価値観を変える」 TECH PLAYを駆使したAGESTの挑戦
事例5.株式会社ココナラ
株式会社ココナラは、応募者の少なさと、採用担当者が少ないことから広報活動に工数をかけられない状況が課題となっていました。
採用活動の成果を高めるべく、同社は少ない工数で集客力が見込めるSNS広告に注力しました。
テレビCM放映期間とSNS広告を打つタイミングを合わせたところ、効果的に自社の魅力をターゲットにアピールできました。
募集ページのPVが10倍以上に増え、幅広い職種のエンジニアを採用できています。
※参考:一度の広告掲載で6名の採用に成功。 ココナラが考えるWantedly広告オプション活用術|株式会社ココナラ
求人サイトによるエンジニアの採用事例2選
さまざまな求人サイトを活用したエンジニアの採用事例を2つ紹介します。
事例6.株式会社モンスターラボ
株式会社モンスターラボは、求人サイトWantedlyを活用し、約1年半で正社員のべ50名を採用しました。
同社は、具体的な内容や関心の高いキーワードを盛り込んで、求人情報を掲載しています。
掲載数に上限はないため、iOSエンジニアなど具体的な職種を指定し、複数の募集を掲載しました。
さらに、募集を繰り返すなかで試行錯誤することで、ターゲットに響く募集のコツを理解できました。
※参考:1年半で60名以上の「会社を一緒につくる仲間」に出会えた!Wantedly運用ノウハウ | SELECK [セレック]
事例7.株式会社ベリサーブ
株式会社ベリサーブは、ハイクラス人材のポテンシャルを見極め、入社動機を高められる採用フローを構築しています。
同社は求人サイトのdodaと連携し、必要なポジションや求める人物像を、応募者に明確に伝えました。
また、事業トップが自らカジュアル面談を実施し、応募者に合わせて、採用フローをカスタマイズしています。
同社はハイクラス人材の獲得に成功し、2022年の1Qから3Qにかけ、内定承諾率が44%から69%に上昇しました。
加えて、40日程度かかっていた採用フローが1か月程度まで短縮できました。
※参考:株式会社ベリサーブ「経験豊富なITエンジニアの獲得に成功」|doda中途採用をお考えの法人様へ
ダイレクトリクルーティングによるエンジニアの採用事例2選
企業から応募者にアプローチする、ダイレクトリクルーティングを活用した採用事例を2つ紹介します。
事例8.株式会社メルカリ
株式会社メルカリは、「求人サイトからの応募者が、自社にマッチするとは限らない」と考えています。
同社は、ダイレクトリクルーティングツールにLinkedInを採用しました。
LinkedInは世界規模のビジネス特化型SNSです。
LinkedInの登録者には豊富なキャリアを持つ人や、英語が堪能な人が少なくありません。
同社はLinkedInの登録者をミートアップイベントに招待し、選考に進んでもらうようアプローチをかけました。
また、採用会食のように、従業員がリファラル採用に取り組みやすい体制も整備しています。
株式会社メルカリが取り組む、エンジニア採用に向けた技術広報について徹底解説した動画がこちらです。
興味のある方はぜひご覧ください。
事例9.富士通株式会社
富士通株式会社は、ビジネス拡大に向け専門性の高い優秀な人材を多数必要としていました。
同社は、3.3万人もの信頼する従業員の「つながり」を活かして、リファラル採用を導入しました。
リファラル採用の成果を高めるべく導入された施策が、「GoToリファラルキャンペーン」です。
キャンペーンは紹介者に1万円のギフト券がプレゼントされる、総額200万円の大がかりなものでした。
同社は、2023年1月時点で累計80名をリファラル採用で獲得し、退職者数は0名です。
また、以前と比較すると、採用活動費を累計で1.2億円削減できているそうです。
※参考:社員3.3万人の人脈を活用!DX企業・富士通が取り組むリファラル採用の秘訣とは |HR NOTE
まとめ
エンジニア採用を成功させるには、各フェーズにおけるコツを抑えて、効果的に求職者にアピールすることが重要です。
本記事で解説したとおり、認知フェーズ・募集フェーズ・内定〜入社フェーズそれぞれにおける採用活動のポイントを抑えた採用活動を行うことにより、優秀なエンジニアを効率的に採用できるようになります。
た、エンジニアの採用ブランディングや組織づくりも、魅力的な職場環境を作り出し、優秀な人材を引きつける重要な要素です。
これらのコツを活用することで、企業はエンジニア採用を成功に導き、持続的な成長を実現できるでしょう。

この記事を書いた人
TECH PLAY BUSINESS
パーソルイノベーション株式会社が運営するTECH PLAY。約23万人※のテクノロジー人材を会員にもつITイベント情報サービスの運営、テクノロジー関連イベントの企画立案、法人向けDX人材・エンジニア育成支援サービスです。テクノロジー人材のエンパワーメントと企業のDX化の成功をサポートします。※2023年5月時点
よく読まれている記事
\「3分でわかるTECH PLAY」資料ダウンロード/
事例を交えて独自のソリューションをご紹介します。