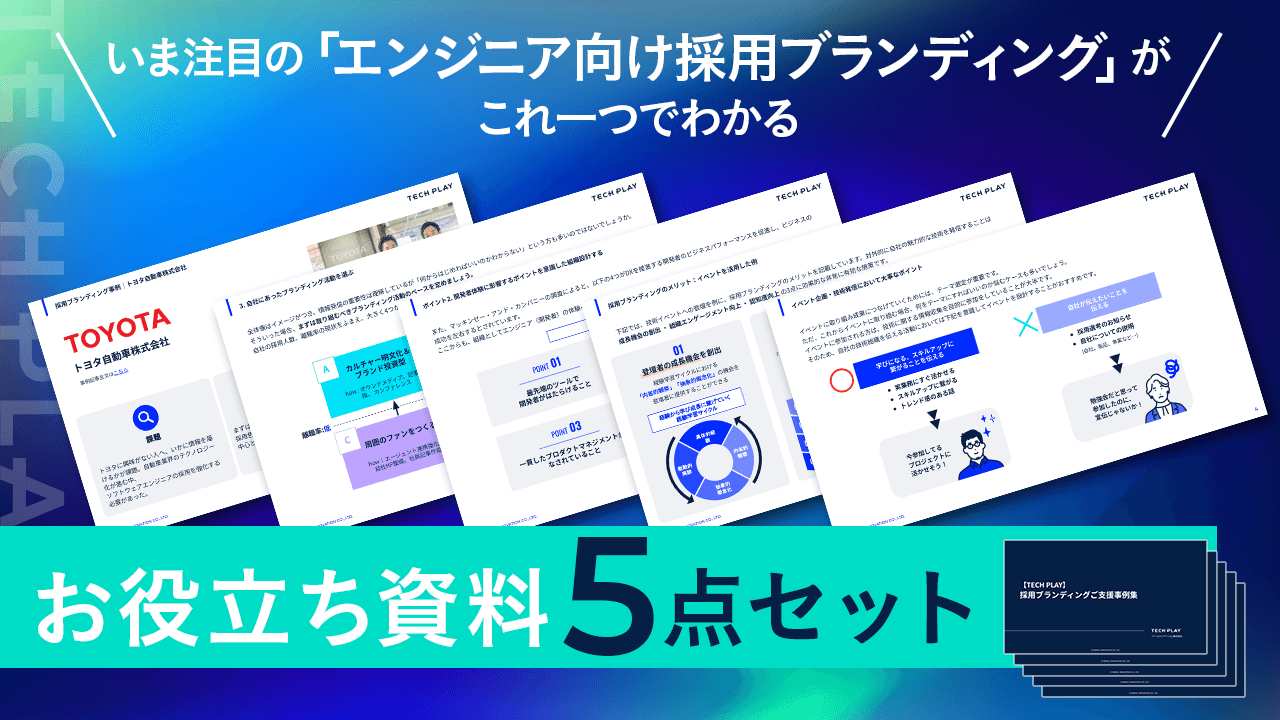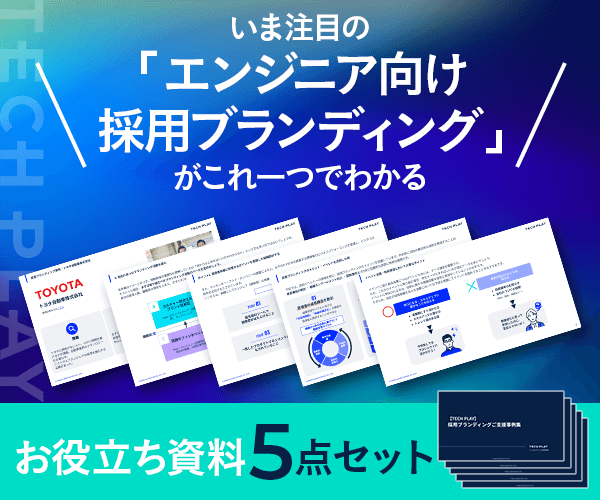エンジニア採用で人事が知るべき3つの知識【採用の流れやポイントも解説】
エンジニア採用を担当する人事の方の中には、「エンジニア採用は他の職種と違い、難しい…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
専門知識が必要な職種であるだけに、適切な採用手法が分からなかったり、選考基準の設定に悩んだりするケースも少なくありません。
さらに、エンジニア採用は競争が激しく、単に求人を出すだけでは優秀な人材に出会えないのが現実です。
そこで本記事では、エンジニア採用を成功させるために人事が押さえておくべき「3つの知識」を解説します。
採用の流れや具体的なポイントも交えながら、エンジニア採用をスムーズに進めるためのヒントをお伝えします。
エンジニア採用に課題を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
人事がエンジニア採用で抱える悩みとは?
エンジニア採用は、一般的な職種とは異なる専門知識が求められるため、多くの人事担当者が「どこから手をつければいいのか分からない」と悩みがちです。
特に、エンジニア職の理解が十分でない場合、適切な採用戦略を立てるのが難しくなります。
ここでは、現状を正しく把握するために、多くの企業の人事担当者が直面しているエンジニア採用に関する4つの代表的な悩みについて解説します。
エンジニア採用の有効求人倍率は10倍超の売り手市場である
経済産業省のIT人材受給に関する調査によると、2030年には最大で約79万人ものIT人材が不足するといわれています。
また、転職サービスdodaが実施した転職求人倍率レポート(2024年8月)によると、2024年8月のエンジニア(IT・通信)の転職求人倍率は12.41倍となっています。
このようにエンジニア採用は超売り手市場であり、企業側が積極的にアプローチしないとエンジニアに出会うことすら難しく、自社の魅力が求職者に伝わらず応募までつながりにくくなってきています。
既存の手法(スカウト、求人広告など)だけでは採用が難しくなってきており、優秀なエンジニアが確保できず悩んでいる人事担当者も多いでしょう。
エンジニア採用に適した採用手法が分からない
前章で解説したように、エンジニア採用市場は競争が激しく、採用手法が多様化してきており、専門知識のない人事担当者にとってはますます採用が難しくなってきています。
求職者であるエンジニアは人材紹介・求人媒体・ダイレクトリクリーティングやSNSなど、多くの選択肢から転職活動を行っています。
人事担当者のエンジニアに対する専門知識が不足している状況では、多様化する採用手法を使い分けるのは非常に困難で、負担に感じる人事担当者も多いでしょう。
エンジニア採用の募集要項の設定方法が分からない
「エンジニアの募集要項を書こうとしても、必要なスキルや経験が分からない…」という悩みはよく聞かれます。
例えば、「Javaができる人を採用したい」と考えていても、実際にどのレベルのスキルが必要なのか、どのように表現すれば適切な応募者が集まるのかが分からず、曖昧な募集要項になってしまうことも。
結果として、企業の求める人材と応募者のミスマッチが発生し、採用に苦戦するケースが多いです。
エンジニア採用に適した選考フローの設定方法が分からない
一般的な事務職や営業職の採用では、書類選考→一次面接→最終面接という流れが一般的です。
しかし、エンジニアの場合は専門的な知識が求められるため、即戦力としての人材を募集する場合、選考フローの中に技術課題を組み込むケースもあります。
人事担当がエンジニアリングに対して深い知識を持っていない場合、具体的にどのような選考フローを組んで良いか分からず、悩んでしまうことも多いでしょう。
また、面接の中で技術的な質問をどの程度すべきかも分からず、結果的に適性を十分に評価できないまま採用の判断を迫られるケースもあります。
書類選考や面接で優秀なエンジニアを見抜くポイントが分からない
「技術的な話になるとよく分からない」「履歴書や職務経歴書を見ても、どのスキルが重要なのか判断できない」という悩みも多いです。
特にエンジニアの場合、スキルや経験は職務経歴書だけで判断しにくく、ポートフォリオやGitHubの内容を確認する必要があります。
しかし、コードを読める人事担当者は少なく、結局「資格があるか」「経験年数が長いか」といった表面的な部分で評価してしまうこともあります。
面接でも、専門的な話になると適切な質問ができず、候補者の本当の実力を見抜けないまま合否を決めなければならない…という不安を感じる人事担当者も少なくありません。
人事が知るべきエンジニアの主な職種一覧
エンジニアと一口に言っても、その職種は多岐にわたります。
開発するシステムや技術領域によって求められるスキルセットや役割が異なるため、採用を成功させるには、それぞれの職種の基本的な違いを理解しておくことが重要です。
ここでは、主なエンジニア職種をカテゴリごとに紹介します。
Web・アプリ開発系
フロントエンドエンジニア
フロントエンドエンジニアは、Webサイトやアプリケーションの「見た目」を作るエンジニアです。
ユーザーが直接触れる部分を担当し、デザインやボタン、画面の表示内容などを整えます。
主に使う技術は、HTML、CSS、JavaScriptなどで、ユーザーが快適に操作できるように工夫します。
サーバーサイドエンジニア
サーバーサイドエンジニアは、Webサイトやアプリの「裏側」を担当します。
ユーザーが何か操作をしたときに、どのように情報を処理するかを考え、サーバーというコンピューターで実行するプログラムを書きます。
使う技術は、PHPやRuby、Pythonなどです。サーバーサイドのエンジニアは、データベースとのやり取りやセキュリティにも関わります。
モバイルアプリエンジニア
モバイルアプリエンジニアは、スマートフォン用のアプリを開発するエンジニアです。
iOSやAndroid向けに、アプリの機能を実現するコードを書きます。
使う技術には、SwiftやKotlin、Flutterなどがあり、スマホならではの動きや操作性を考えて開発します。
システム・インフラ系エンジニア
インフラエンジニア
インフラエンジニアは、システムがスムーズに動作するために必要な「基盤」を作るエンジニアです。
サーバーやネットワーク機器の設置、管理を行い、システム全体の運用を支える役割を担っています。
AWSやGCPなどのクラウドサービスの知識が求められ、システムの安定稼働やスケーラビリティを考慮した設計が重要になります。
ネットワークエンジニア
ネットワークエンジニアは、コンピュータやサーバーを繋げる「ネットワーク」を作り、管理するエンジニアです。
ネットワークが正常に動作するように設計や設定を行い、トラブルシューティングも行います。
インターネットの通信速度やセキュリティにも関わります。
データベースエンジニア
データベースエンジニアは、データベースという情報を整理して保存する仕組みを作るエンジニアです。
データを効率よく管理し、検索や更新がスムーズに行えるように設計します。
主に使う技術は、SQLやMySQL、PostgreSQLなどのデータベース管理ツールです。
データ・AI関連エンジニア
データエンジニア
データエンジニアは、大量のデータを処理・整理する役割を担うエンジニアです。
データが有用な情報に変わるように、データの収集や管理、加工を行います。
使う技術には、PythonやSQLが多く、ビッグデータの分析にも対応できるスキルが求められます。
機械学習エンジニア
機械学習エンジニアは、コンピュータが自分で学習し、予測や判断をする仕組みを作るエンジニアです。
AI(人工知能)を活用して、データからパターンを学び、将来の結果を予測したり、最適な行動を導き出したりします。
PythonやTensorFlowなどのツールを使って、モデルを作り上げます。
セキュリティ・品質管理系エンジニア
セキュリティエンジニア
セキュリティエンジニアは、システムを外部の攻撃から守るための技術者です。
ハッキングやウイルス感染、情報漏洩などを防ぐため、セキュリティ対策を強化します。
暗号化技術や侵入検知システムを活用して、システムを安全に保つ役割を担っています。
QAエンジニア
QAエンジニア(品質管理エンジニア)は、ソフトウェアやシステムが期待通りに動くかをチェックする役割を担うエンジニアです。
バグやエラーがないかテストを行い、品質が高い状態でリリースされるようにします。
手動テストや自動化テストを行い、問題を早期に発見します。
その他のエンジニア
ゲームエンジニア
ゲーム開発に特化したエンジニアで、UnityやUnreal Engineを使って3Dゲームを開発したり、ゲーム内の物理エンジンやAIを実装したりします。
ゲームの特性上、リアルタイム処理やグラフィック技術に精通している必要があります。
組込・制御系エンジニア
組込・制御系エンジニアは、家電製品や車、工業機械などの「組み込まれたコンピュータ」を開発するエンジニアです。
マイコン(マイクロコントローラー)を使って、ハードウェアとソフトウェアが連携して動くようにプログラミングします。
C言語やアセンブリ言語がよく使われます。
人事が知るべきエンジニアの主な職位一覧
エンジニアの職位は、経験やスキル、役割によって異なります。
採用する際には、職位ごとに求められるスキルや責任範囲を理解し、適切なポジションでの採用を行うことが重要です。
本章では、エンジニアの主な職位とその役割をまとめました。
ジュニアエンジニア
エンジニアとしてのキャリアをスタートしたばかりの新人エンジニアです。
主に先輩エンジニアの指導を受けながら、小規模な開発業務やテストを担当します。
求められる経験やスキルは、以下のとおりです。
- 基本的なプログラミング知識(例:JavaScript、Python、Java など)
- コードの読み書きやバグ修正ができる
- Git などのバージョン管理ツールの基本操作
システムエンジニア(SE)
システムの設計から開発、テスト、運用までを担当するエンジニアです。
プログラムを書くこともありますが、要件定義や仕様設計など上流工程を担うことが多いです。
求められる経験やスキルは、以下のとおりです。
- 要件定義・基本設計・詳細設計の経験
- データベースやサーバーの基礎知識
- クライアントとの折衝能力
リードエンジニア
開発チームの技術的なリーダーとして、メンバーのコードレビューや技術的な意思決定を行うエンジニアです。
チーム内の技術水準を向上させる役割を持ちます。
求められる経験やスキルは、以下のとおりです。
- 実務経験5年以上が目安
- コードレビューや技術指導の経験
- プロジェクト全体を俯瞰し、技術選定や開発方針を決定できる
シニアエンジニア
深い専門知識と豊富な経験を持つエンジニアです。
特定の技術領域に精通し、難易度の高い技術課題の解決を担うことが多いです。
求められる経験やスキルは、以下のとおりです。
- 実務経験7年以上が目安
- 高度なアルゴリズム・データ構造の知識
- 大規模システムの設計・開発経験
プロジェクトリーダー(PL)
開発プロジェクトのリーダーとして、メンバーの進捗管理やタスク分担を行い、プロジェクトを成功へと導く役割を担います。
求められる経験やスキルは、以下のとおりです。
- プロジェクト管理の経験
- 要件定義や仕様策定のスキル
- チームマネジメント能力
テックリード
技術面での意思決定を担当し、開発チームの技術的な方向性を示すポジションです。
技術選定やコードの品質向上をリードします。
求められる経験やスキルは、以下のとおりです。
- モダンな開発技術に関する深い理解(例:マイクロサービス、クラウド技術など)
- コードレビューや設計レビューを主導できる
- 他のエンジニアへの技術的な指導経験
アーキテクト
システム全体の設計を担当し、適切な技術スタックやシステム構成を決定するエンジニアです。
スケーラビリティやパフォーマンスを考慮した設計を行います。
求められる経験やスキルは、以下のとおりです。
- システム設計・アーキテクチャ設計の経験
- クラウドや分散システムの知識
- 大規模システムの運用経験
プロジェクトマネージャー(PM)
プロジェクトの計画・進行管理を担当し、納期や予算、品質を管理するポジションです。
開発チームだけでなく、経営層やクライアントとも連携します。
求められる経験やスキルは、以下のとおりです。
- プロジェクト管理ツール(JIRA、Redmine など)の使用経験
- スケジュール・コスト管理の知識
- ステークホルダーとのコミュニケーション能力
最高技術責任者(CTO)
企業の技術戦略を担う経営層のポジションです。
新技術の導入、エンジニア組織の構築、事業の成長戦略を技術面からリードします。
求められる経験やスキルは、以下のとおりです。
- 技術とビジネスの両方に精通している
- エンジニアチームの組織運営・マネジメント経験
- 長期的な技術戦略の策定・実行経験
人事が知るべきエンジニアの採用手法一覧
エンジニア採用において、採用手法の選択は非常に重要です。
求める人材のスキルレベルや経験、企業の採用予算、ブランド力などによって、適した手法が異なります。
ここでは、主要なエンジニア採用手法を解説します。
求人広告・転職サイト
求人広告や転職サイトを活用することで、多くの求職者に自社の求人情報を届けることができます。
特に、エンジニア向けの専門サイト(Green、Findy、Qiita Jobs など)では、IT業界に特化した求職者が集まりやすいのが特徴です。
また、大手転職サイト(リクナビNEXT、doda、マイナビ転職など)でも、エンジニア向けの求人枠が用意されています。
この手法のメリットは、幅広い層にアプローチできる点ですが、一方で競合他社と求人が並ぶため、自社の魅力をしっかり打ち出さなければ埋もれてしまうリスクもあります。
また、応募者のスキルレベルにばらつきがあるため、選考に時間がかかることもあります。
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングは、企業側から求職者に直接アプローチする採用手法です。
転職サイトに登録しているエンジニアに対して、スカウトメールを送る形が一般的ですが、LinkedInやForkwellといったプラットフォームを活用することもあります。
この手法のメリットは、企業が求めるスキルや経験を持つ人材にピンポイントでアプローチできる点です。
しかし、エンジニアはスカウトメールを多く受け取るため、テンプレート的な内容では見向きもされません。
しっかりとパーソナライズされたメッセージを送ることが、成功の鍵となります。
エージェント
人材紹介エージェントを利用すると、企業の求める条件に合った候補者を紹介してもらえます。
エージェントは転職希望者と事前に面談を行っているため、企業側が求めるスキルやカルチャーフィットに合う人材を紹介してもらいやすいのが特徴です。
この手法のメリットは、採用担当者の負担を軽減しながら、比較的即戦力となる人材と出会えることです。
ただし、成功報酬型が一般的であり、採用1人あたりの費用が高額になることがデメリットです。
コストを考慮しながら、他の採用手法と組み合わせて活用するのが効果的でしょう。
SNS・コミュニティ採用
Twitter(X)や、GitHub、Qiita、Zenn、Stack Overflow などのエンジニア向けプラットフォームを活用し、企業の採用情報を発信したり、優秀なエンジニアに直接アプローチしたりする手法です。
また、エンジニア向けの勉強会やMeetupに参加し、企業の魅力を伝えることで、自然な形で採用につなげることもできます。
この手法のメリットは、エンジニアとの関係性を築きながら、企業の技術力やカルチャーを伝えられる点です。
しかし、短期的に採用成果を出すのは難しく、継続的な情報発信やコミュニティへの貢献が求められます。
リファラル採用
リファラル採用とは、社員の紹介を通じてエンジニアを採用する方法です。
既存の社員が知人や前職の同僚などを推薦するため、企業のカルチャーに合った人材が見つかりやすく、入社後の定着率も高くなる傾向があります。
この手法のメリットは、採用コストが比較的低く、信頼できる人材と出会いやすいことです。
一方で、社内のネットワークに依存するため、母集団が限定的になる点がデメリットとなります。
紹介制度の仕組みを整え、社員に積極的に活用してもらうための工夫が必要です。
ハッカソン・イベント採用
ハッカソンやプログラミングコンテストを通じて、優秀なエンジニアと出会う採用手法です。
企業が主催するハッカソンを開催したり、既存のイベントにスポンサーとして参加したりすることで、技術力の高い人材と接点を持つことができます。
この手法のメリットは、応募者の実際の技術力を見極めながら採用できる点です。
また、企業の技術ブランディングにもつながります。
ただし、イベント運営にはコストや工数がかかるため、目的を明確にした上で実施する必要があります。
新卒・ポテンシャル採用
新卒採用やポテンシャル採用は、実務経験のない若手エンジニアを育成することを前提とした採用手法です。
企業独自の研修プログラムやOJTを通じて、長期的に育成することを目的としています。
この手法のメリットは、企業の文化に合った人材を育成できることです。
また、即戦力採用に比べて競争が激しくないため、優秀な人材を確保しやすい場合もあります。
ただし、未経験エンジニアの教育・育成には時間とコストがかかるため、適切な研修体制やメンター制度を整えることが成功の鍵となります。
エンジニアの新卒採用やポテンシャル採用に関しては、それぞれ以下の記事でさらに詳しく解説していますので、興味のある方はぜひご覧ください。
・新卒採用について
【エンジニアを採用する5つの方法】メリット&デメリットと成果を最大化する手法を解説
・ポテンシャル採用について
エンジニアのポテンシャル採用とは?実施する際のポイントやメリットなども紹介!
人事がエンジニアを採用するまでの流れ・ポイント
IT業界は慢性的な人材不足の状態にあり、優秀なエンジニアの獲得は多くの企業にとって大きな課題となっています。
そのため、採用活動を成功させるには、事前準備をしっかりと行い、求める人材を明確にし、ターゲットに適した採用手法を選択することが重要です。
ここでは、採用の流れを2つのフェーズに分け、それぞれのポイントを詳しく解説します。
採用計画フェーズ(事前準備)
競合調査と市場分析を行う
エンジニア採用の成功の第一歩は、競争環境の理解です。
現在のIT市場では、エンジニアの採用難易度が高まり、特定のスキルを持つ人材を確保することが困難になっています。
そのため、まずは競合企業がどのようなポジションのエンジニアを採用しているのか、求人の給与相場はどの程度なのか、業界全体のトレンドや求められているスキルセットを調査することが不可欠です。
市場分析の際には、求人情報サイトやエンジニア向けの転職サービスを活用し、他社の募集要項を確認するのが有効です。
また、エンジニア向けのSNS(X(旧Twitter)、LinkedInなど)や技術ブログをチェックすることで、どのような働き方や技術が注目されているのかを把握できます。
これらの情報をもとに、自社の採用活動においてどのような差別化ができるのかを考えましょう。
自社の魅力や特徴を整理する
エンジニアは、単なる給与や待遇だけでなく、企業の技術力や経営方針、成長環境などを重視する傾向があります。
そのため、自社の強みや魅力を整理し、採用活動に活かすことが重要です。
例えば、以下のようなポイントを明確にすることで、ターゲットとするエンジニアにアピールしやすくなります。
- 技術的な強み(使用技術、開発手法、技術スタック)
- 成長環境(技術研修、勉強会の実施、資格取得支援制度)
- 働きやすさ(リモートワークの可否、フレックスタイム制、副業の許可)
- 企業文化(技術コミュニティへの参加、OSSへの貢献、開発の自由度)
また、現場のエンジニアにヒアリングを行い、実際の開発環境や働き方を整理することも効果的です。
こうした情報を採用ページや採用資料に反映し、候補者に伝えられるようにしましょう。
採用ターゲットを明確にする
採用活動を進めるうえで、「どんなエンジニアを採用したいのか」を明確にすることは非常に重要です。
求めるスキルや経験年数が曖昧なまま進めてしまうと、採用基準がブレたり、ミスマッチが発生したりする可能性があります。
ターゲット設定の際には、以下の点を具体的に定めるとよいでしょう。
- 必須スキルと歓迎スキル(言語、フレームワーク、クラウド技術など)
- 経験年数(ジュニア、ミドル、シニアなど)
- 開発スタイルの適性(アジャイル、ウォーターフォールなど)
- 求める人物像(リーダーシップ、問題解決能力、協調性など)
特に、現場のエンジニアやマネージャーと協議しながら、具体的な人物像をすり合わせることが重要です。
現場のエンジニアを巻き込む
エンジニアは専門職であるため、知識のない人事担当者だけで選考を進めると、専門スキルの適切な評価が難しく、応募者の能力を見極められない可能性があります。
そのため、現場で働くエンジニアを巻き込み、求人情報や具体的な採用プロセスを改善することが重要です。
採用プロセスにエンジニアが関わることで、より求職者に刺さる訴求ができ、専門スキルを適切に評価できるため、優秀なエンジニアを採用できる可能性が高まります。
また、現場で働くエンジニアの新入社員に対する仲間意識も高まるため、社員同士がコミュニケーションを取りやすい雰囲気になりやすいため、入社後の定着率向上にもつながります。
このように、現場で働くエンジニアの意見を採用活動に反映させることが、採用を成功させるためのポイントの一つです。
採用要件を明確にする
採用ターゲットを定めたら、具体的な要件を求人票に落とし込む必要があります。
求人票を作成する際には、単にスキルセットを列挙するのではなく、「実際にどのような業務を担当するのか」を明確に伝えることが大切です。
例えば、以下のような具体的な表現を心がけましょう。
NG例:「Reactを使用したフロントエンド開発を担当」
OK例:「ユーザー向けのダッシュボード開発を担当。Reactを使用し、パフォーマンス最適化やUI/UX改善にも携わる」
こうした工夫をすることで、応募者は実際の業務内容をイメージしやすくなり、ミスマッチを防ぐことができます。
採用手法・戦略を決定する
エンジニア採用の手法には、以下のような選択肢があります。
- 求人広告・転職サイト(リクナビNEXT、Green、Forkwellなど)
- ダイレクトリクルーティング(Wantedly、LinkedIn、BizReachなど)
- リファラル採用(社内紹介制度)
- エージェント活用(IT特化型の転職エージェント)
- ハッカソン・技術イベント採用(技術力を直接確認できる場)
どの手法を活用するかは、採用ターゲットや予算によって決まります。
複数の手法を組み合わせながら、効率的な採用活動を目指しましょう。
予算とリソースを確保する
採用活動には、求人掲載費、スカウト費用、エージェント手数料、イベント運営費など、多くのコストが発生します。
また、人事担当者の工数も考慮する必要があります。
事前に必要なコストを試算し、経営層と調整しながら予算を確保することが重要です。
特に、エンジニア採用は即戦力を求める場合が多いため、予算を低く設定しすぎると結果的に採用が長引いてしまい、さらなるコストが発生してしまうこともあります。
認知〜採用活動実施フェーズ
エンジニア採用では、事前準備を整えた後、実際にターゲットへ自社の魅力を伝え、応募を促すフェーズに移ります。
ただし、エンジニアは常に複数の企業からアプローチを受けており、受け身の採用ではなかなか思うように人材を獲得できません。
そのため、認知拡大から応募までの流れを戦略的に進める必要があります。
ここでは、認知〜採用活動実施フェーズのポイントを詳しく解説します。
企業・技術ブランディングを強化する
エンジニア採用においては、「どのような技術を扱い、どんな開発環境があるのか」という企業の技術的な魅力が重視されます。
これは、給与や福利厚生以上に、「自分のスキルが成長する環境か」「興味のある技術に触れられるか」といった観点が、エンジニアの転職動機に直結しているからです。
そのため、採用活動と並行して技術ブランディングを強化することが不可欠です。
しかし、効果的な採用ブランディングを実践するには、適切な発信手法やエンジニアとの接点を持つ場が不可欠です。
そこでおすすめなのが、採用ブランディング支援サービス「TECH PLAY Branding」 です。
TECH PLAY Brandingは、エンジニア向けのイベントやコミュニティ運営を通じて、企業の技術力やカルチャーをアピールし、採用につなげるためのサービスです。
特に、採用サイトや技術ブログ、SNS、イベントなどを活用し、企業の強みや開発環境、カルチャーを継続的に発信することは、エンジニアからの共感を得る上で非常に有効です。
TECH PLAY Brandingを活用すれば、企業とエンジニアが直接つながる場を作ることができ、より深い関係を築くことができます。
このように採用ブランディングを強化することで、「この企業で働きたい」と思うエンジニアが増え、結果として応募数の増加や選考辞退率の低下につながります。
魅力的な求人情報を作成する
求人情報は、エンジニアにとって企業の最初の印象を左右する重要なコンテンツです。
ただし、単に業務内容や条件を羅列するだけでは、他社の求人と埋もれてしまいがちです。
エンジニアは「自分がどんなプロジェクトに関われるのか」「どんな技術に触れられるのか」を重視するため、求人情報では以下のようなポイントを具体的に盛り込む必要があります。
- プロジェクト内容
- チーム構成と開発体制
- 成長環境とキャリアパス
こうした具体的な情報を提示することで、応募者は入社後のイメージを持ちやすくなり、応募意欲が高まります。
策定した戦略に従って採用活動を実施する
事前に策定した採用戦略に基づき、具体的な活動を展開していきます。
計画だけに留まらず、状況を見ながら柔軟に修正を加えていくことが、成功の鍵となります。
採用活動の実施時には、以下のポイントを意識しましょう。
- 複数の採用チャネルを並行活用する
- ダイレクトリクルーティングを積極的に活用する
- 進捗状況を定期的に振り返る
- エンジニアチームと密に連携する
採用活動は「計画→実施→評価→改善」を繰り返すことが重要です。
このサイクルを意識することで、より質の高い採用を実現できます。
さらに、エンジニア採用が成功し、内定〜入社の段階で意識するべきポイントは、以下の記事で詳しく解説していますので、興味のある方はぜひご覧ください。
エンジニア採用は難しい?苦戦する理由とやるべき17の対策【成功事例あり】
人事が効率的にエンジニアを採用するなら「TECH PLAY Branding」がおすすめ
社内リソースによるエンジニア採用に限界を感じているという企業におすすめなのが、エンジニア向け採用ブランディングサービス「TECH PLAY Branding」 です。
「TECH PLAY Branding」はパーソルイノベーション株式会社が運営する、27万人以上のエンジニア・デジタル人材にアプローチができる採用支援サービスです。
エンジニア採用に詳しい専門メンバーが、採用戦略の立案からエンジニア向けイベントの企画・運営までを支援します。
自社の技術力や開発環境を直接アピールできるイベントを企画・運営しており、エンジニアとの接点を増やし、興味を持ってもらいやすくなります。
単なる採用活動ではなく、エンジニアにとって魅力的な企業として認知されることで、長期的な採用成功につながります。
イベントだけでなく、TECH PLAYのプラットフォームを活用し、エンジニアに向けた情報発信ができるため、興味を持った層にダイレクトにアプローチできます。
従来の採用手法に限界を感じているなら、TECH PLAY Brandingの導入をぜひ活用を検討してみてください!
まとめ
エンジニア採用は、専門知識の壁や市場の競争の激しさから、他の職種と比べて難易度が高いと言われます。
しかし、人事担当者が採用のポイントを押さえ、戦略的に進めることで、優秀なエンジニアと出会える確率は大きく上がります。
本記事では、エンジニア採用で人事が知るべき知識や、採用の流れやそれぞれの工程における意識するべきポイントを解説しました。
これらの知識を活用し、自社に合った採用戦略を構築することが成功の鍵となります。
エンジニア採用は一朝一夕で成果が出るものではありませんが、地道な取り組みが大きな成果につながります。

この記事を書いた人
TECH PLAY BUSINESS
パーソルイノベーション株式会社が運営するTECH PLAY。約23万人※のテクノロジー人材を会員にもつITイベント情報サービスの運営、テクノロジー関連イベントの企画立案、法人向けDX人材・エンジニア育成支援サービスです。テクノロジー人材のエンパワーメントと企業のDX化の成功をサポートします。※2023年5月時点
よく読まれている記事
\「3分でわかるTECH PLAY」資料ダウンロード/
事例を交えて独自のソリューションをご紹介します。